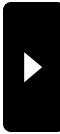2025年03月11日
本堂に座って 2025年3月

2025年02月04日
本堂に座って 2025年2月

2025年01月06日
本堂に座って 2025年1月

2024年12月26日
本堂に座って 2024年12月

2024年11月08日
本堂に座って 2024年11月

今月も先月に引き続き平川宗信先生の講演録を紹介します。今回は、非暴力・不服従抵抗について、まとめのお話です。
<非暴力・不服従抵抗の有効性>
非暴力・不服従抵抗で勝てるかと言えば勝てる保証は必ずしもありません。すぐに効果が出てくるかと言えば必ずしもそうではありません。長い時間がかかることもあり得ます。犠牲者が出ないかと言えば、そうとは限りません。そのことは覚悟しておかなければなりません。とはいえ軍事力で抵抗すれば勝てるのか、戦争はすぐに終わるのか、犠牲者を出さずに済むのかと言えば、そんなことはないわけです。平和学の研究によれば、軍事抵抗よりも非暴力・不服従抵抗の方が成功率は高いとされています。紛争が早く終わる可能性も犠牲が少なくて済む可能性も高いと言われています。軍事力の方が防衛力として優位にあるわけではないということです。
<非暴力・不服従抵抗の相手>
そして「平等」も、仏教の基本だと思います。非暴力・不服従抵抗は、平等というところに立つ防御方法です。万一、日本に外国軍の兵士が侵入してきたとしても、この人たちを「敵」とは見ません。私たちと同じ人間であると、平等に見ます。
非戦・非武装で平和外交をしている国に武力侵攻をするのは、明らかに国際法違反の犯罪、侵略罪に当たります。侵入してくる国の政府は、国際犯罪を行っている不法・不当な政府ということになります。その政府の命令によって送られてきた兵隊は、いわば犯罪的な政府にだまされて、犯罪的な行為に加担させられている人たちということになります。非暴力・不服従抵抗は、その人たちに「あなた方はだまされているのですよ、あなた方は犯罪的なことに加担させられているのですよ」と言って、そのことを理解し、自覚してもらうのです。理解し、自覚してもらうことによって、その人たちを不法・不当な政府から解放し、占領の道具として使われることから離脱してもらうのです。そうなると、占領はもう不可能になります。
<非暴力・不服従抵抗で守るもの>
非暴力・不服従抵抗では領土に外国軍が入ってくることを止めることはできません。その意味では領土を守り国を守ることは、非暴力・不服従抵抗ではできません。軍事的防衛は、国を守るのです。その時国民はどのような立場に置かれるかというと、国を守るためにいのちを捨てさせられるのです。これが軍事力による防衛です。非暴力・不服従抵抗は、国を守るのではありません。自分たちで自分たちのいのちと暮らしを守るのです。私はこれが非暴力・不服従抵抗の意味だと思っています。
念仏者が阿弥陀さまからいただくお仕事は、国を守ることではないと思います。阿弥陀さまは、いのちを捨てて国家を守れとはおっしゃっておられません。阿弥陀さまは、全てのいのちが共に生きる世界をつくりなさい、そのような世界を守りなさい、そのために全ての人々のいのちと暮らしを守っていきなさい、そのことに身を粉にし、骨を砕いていきなさいと、おっしゃっていると思うのです。私たちは、その願いに立って、全ての人々が共に生きていける世界、全ての人々のいのちと暮らしが守られる世界をつくるために、日々の暮らしの中で、それに向けた行いを積み重ねていく。そのことが重要だと思います。
非暴力・不服従抵抗は、自分の国の政府が不法・不当なことをしている場合にも、それを止めるために行われるものです。この国の政府が、この国を地獄・餓鬼・畜生の国にしようとしたり、人々のいのちと暮らしを侵害したりするような場合には、この国の政府に対しても非暴力・不服従で抵抗しなければならないと思っています。
<おわりに>
今、多くの人が危機感をあおられて、軍事力に頼ろうとしているように思えてなりません。しかし、軍事力は鬼神だと思います。頼もしく見えるけれども、ついていくととんでもないことになっていくのが、鬼神である軍事力だと思うのです。
私たちはどこまでも本願を信じ、本願を恃み、鬼神は信じない、軍事力には頼らない。これが念仏者の生き方だと思います。その意味で今、私たちは「本願を恃むのか、それとも鬼神である軍事力を頼むのか」と、厳しく問われていると思います。
(『真宗』2024年6月号 東本願寺出版発行
念仏者の「非戦・非武装」に立つ平和運動 より引用しました)
2024年10月23日
本堂に座って 2024年10月

2024年10月23日
本堂に座って 2024年9月

2024年10月23日
本堂に座って 2024年8月

本山・東本願寺から毎月発行されている『真宗』誌2024年6月号に、4月2日に勤められた全戦没者追弔法会において平川宗信先生が話された講演録が掲載されました。平川先生は以前から「憲法と真宗」についてお話をされていましたが、特に「日本国憲法と阿弥陀仏の本願」の関わりについて話してくださっています。お話の概要を、今月から数回にわたって紹介します。
<無三悪趣の願>
平和運動との関係で、本願は何を願っているのか。四十八願の第一願「無三悪趣の願」は、「地獄・餓鬼・畜生のない世界をつくる」という願です。これが阿弥陀さまの第一願、最初に置かれている願です。現代社会において「地獄・餓鬼・畜生」とはいったい何だろうかと考えますと、例えば、暴力・戦争などは「地獄」である。飢餓・欠乏・貧困、また貪欲などは「餓鬼」である。そして抑圧・隷従・差別などは「畜生」である。このように読み解くことができると思います。そして、この願いが成就した世界が『仏説無量寿経』に説かれた「国豊民安 兵戈無用」の世界です。国が豊かで民が安穏であり、兵隊も武器もない世界。そのように説かれています。その意味で本願は、暴力や戦争や軍事力がなく、飢餓や貧困や搾取もなく、そして抑圧や隷従や差別もない世界。そういう世界を願っていると言っていいだろうと思います。
最近「平和学」という学問が形成されつつありますが、そこでは、戦争や暴力のない状態を「消極的平和」と言います。そして、貧困や抑圧や差別がない状態を「積極的平和」と言います。さらに、戦争や暴力や抑圧や差別を正当化したり、助長したりする宗教・思想・芸術などがない状態を「文化的平和」と言います。単に暴力や戦争がないというのは、消極的な平和にすぎないのだと。それに加えて、貧困や抑圧や差別がない積極的平和、そして戦争や暴力や抑圧や差別を正当化・助長するような文化がない文化的平和があって、初めて本当の意味での平和が実現するのだと。最近の平和学では、そのように言われています。真宗が願っている平和、日本国憲法が願っている平和も、まさにそういうものではないかと思います。それを追求するのが、いわば真宗の平和主義であり、日本国憲法の広い意味での平和主義だと言うことができるのではないかと思うのです。ですから、念仏者の平和運動は、その願いを持って、そのような世界、国を実現していこうという運動ではないかと思います。いわば、日々の生活、日々の行動の中で、そのような願いを実現することにつながる行いを積み重ねていく。たとえ小さなことでもいい、ささやかなことであってもいいけれども、その願いに適うような行いを日々積み重ねていく。私は、それが大事なことではないかと思います。
<日本国憲法は「本願国家宣言」>
このような所に立って見ますと、現在の日本国憲法は、高く評価できる憲法ではないかと思います。日本国憲法は前文で、国際協調によって平和を維持していくと宣言し、地上から専制・隷従・圧迫・偏狭・恐怖・欠乏をなくすと誓約しています。その上で、第九条で戦争を放棄し、戦力の不保持と交戦権の否認を定めています。これは、戦争や軍事力のない世界、地獄・餓鬼・畜生のない世界を願っている本願と、まさに重なっています。それで私は「日本国憲法は本願国家宣言である」と言ってきているのです。
問題は、私たちが本願の願いである「地獄・餓鬼・畜生のない、豊かで安穏な非戦・非武装の世界」、憲法が求める「専制・隷従・圧迫・偏狭・恐怖・欠乏のない非戦・非武装の世界」を実現するために努力してきたのかということだと思います。私たちは念仏者として、真摯に平和活動・平和運動をしてきたのか。そのことが、今まさに私たちに問われているのではないかと思います。私たちの中にも「地獄・餓鬼・畜生」があります。暴力的なもの、貪欲なもの、差別的なものをいっぱい抱え込んでいます。けれども、それに流されるのではなく、それを脇に置いて本願に聞いて、本願に生きる生き方をしていく。そのための小さな行いを日々重ねていく。それが念仏者であろうと思います。それが、今私たちに願われていることではないかと思うのです。
(『真宗』2024年6月号 東本願寺出版発行
念仏者の「非戦・非武装」に立つ平和運動 より引用しました)
2024年10月23日
今日も快晴!? 2024年8月

2024年07月08日
本堂に座って 2024年7月