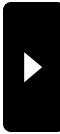2024年10月23日
清風 2024年10月

私は 草であり 牛であり 大地である
ゴータマ・シッダルタ
寺報「清風」の2024年6月号では「人間(私)は、与えられているから悩む」を、同7月号では「実るほど 頭を垂れる 稲穂かな」ということわざを紹介し、同8月号では「何か大きな空虚が、日本人の思想の根底に有るのじゃないだろうか。一言でいえば、生きるということの根本感覚を喪失し、生きるための手段で困憊しているのだと思います。」という言葉を挙げさせてもらいました。
現代人には生活感との関わりが開かれていない…ということから6月号で紹介した「人間(私)は、与えられているから悩む」という言葉について考えてみます。日常生活の中で「悩む」ことは、視点を変えれば「思いも及ばない経験をしている」ことであると言えます。ところがその経験を「当たり前」と評価してしまうことから、日常生活の経験の重みをまったく感じられなくなっている(平凡の繰り返し、というくらいにしか思えない)、私どもの感性の衰弱を自覚できていないのです。
またその経験を「思いも及ばない経験」とは思えずに生活しているため、「目覚め(気づき)」の契機にはなかなかならないという事態に陥っています。便利で快適な生活は実現したのですが、それは成ってみれば、私にとってはすべて「当たり前」でしかないということなのでしょう。
「当たり前」という評価・判断は、本来は物・道具の世界の基準なのです。
一生とは ないものねだりの 歳月か 得てはすぐ慣れ 無くて欲しがる
(朝日歌壇)
この短歌は、「当たり前」という評価しかできない人に与えられている生活の実情を表す典型と言えるのではないでしょうか。ここでも私どもは、「人間(私)は、与えられているから悩む」の言葉で問われているということでしょう。
この言葉は、漫画家の水木しげるさんのエピソードから、私の言葉として表現し直してみたものです。それは水木さんが「あなたにとって、幸せとは何ですか」と問われた際に「呼吸のできることです」と返されたことによります。「呼吸のできること」は、まったく「当たり前」のことでしょう。
さて、この水木さんの応答について、皆さんはどう思われますか。
南無阿弥陀仏 人と生まれた意味をたずねていこう
ここで、ゴータマ・シッダールタが下山して、苦行で衰弱した身体を養生した時の経験に学ぶことにしましょう。
冒頭に掲げた「私は草であり、牛であり、大地である」という言葉は、下山されて養生されている時に気づかれたこととして語られていることです。出家され、6年に及ぶ苦行で衰弱した身体を、消化がよくて栄養がある、病人食とも言われていた「乳粥」の供養を受けられた折に感得された言葉と伝えられています。
「乳粥」は牛乳を発酵させてできるもので、「私は草であり、牛であり、大地である」とは、乳粥のできる過程を表現した言葉ともいえます。その乳粥が、ゴータマの体内で消化され、その栄養が血液によって運ばれ、身体全体に精気が戻り、再びブッダガヤで瞑想に入られました。
その七日七夜の明け方に悟りを開かれ、その言葉は次のようだったと伝えられています。
「我は不死を得たり」 「我は生死を超えたり」
この言葉こそが、やがて「南無阿弥陀仏」という言葉として結晶されていったのです。愚痴の法然房、愚禿親鸞の名告りとともに、伝えられています。
2024年10月23日
お庫裡から 2024年10月

現憲法の前文は、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
と始まります。
私はまだ決まっていない自民党の総裁選に関心があります。モリカケサクラと問題のあった安倍元首相の不運な事件の後、次々明らかになってきた旧統一教会との関係、国際勝共連合とのつながり、派閥の裏金問題、そのどれもが解明されないまま、9名の候補者は次々と「私が選ばれたら」と政策を披露しています。
民主主義は、自由や平等を確保させる一つの手段ですが、国会は議論をせぬまま多数決で強行採決、政府も大事なことを国会に諮らず政府主導で事を推し進めている。私は今の政府の行為で取り返しのつかぬ事態にならぬか危惧しています。
私はもう後期高齢者で未来が長い訳ではありません。それでも「誰が首相になっても同じ」「世の中変わらない」と、無関心であってはならないと思います。
子や孫が戦死者の数に入らないよう、どうすればよいか。ガザやウクライナにならないために日本はどうすればいいか。またイスラエルやロシアと同じことを日本がしないようにどうすればいいか。
武力では決して人は守れない。(9月22日記)
2024年10月23日
今月の掲示板 2024年10月

世の中の役に立つかどうか
有用性で人間を判断する社会になれば
社会全体が命の意味を見失うことになる
何があっても
私が生きていることの意味を
見失わない
私が生きてきたことを
軽く見ない
どう生きぬくことが
自分自身を生きぬくことになるのか
何故苦しむのか
それは
真実を求めているから
尊厳ある生き方というのは
いのちの意味を
見出し続けようとすることではないか
何も信じられない
というただ中に
真実を求める心が現にある
人間の苦悩であり
私の苦悩でもあるような
そういう苦悩を引き受けて
それに応えた人に出会うこと
自分の苦しみを
自分に先んじて知っている人がいる
その苦しみを引き受けて
歩んだ人がいる
2024年10月23日
本堂に座って 2024年10月

今月も先月に引き続き平川宗信先生の講演録を紹介します。今回は、軍事力を頼りにするのか、非戦・非武装、非暴力・不服従抵抗についてのお話です。
<鬼神を頼むのか、本願を恃むのか>
私は軍事力は『教行信証』化身土巻にある「鬼神」だと思います。「鬼神」は非常に強い力を持っていて、頼りにすれば自分たちを守ってくれるように見える。しかし不正直で人をたぶらかし、一つ間違えて怒らせると大変な災いを振り掛けてきて、最後はいのちを奪われるような存在…ではないかと思うのです。親鸞聖人は、「鬼神を信じるな、鬼神を頼むな」ということを『教行信証』化身土巻で繰り返しおっしゃっています。私たちは鬼神である軍事力を頼りにしてはいけないと思うわけです。
本願は日本人だけではなく、世界中の人々に届いています。本願には世界中の人々のいのちに呼びかけて、平和を愛する人、平和を願う人に変える力があると、私は信じています。私たち念仏者はその本願の力、本願力を信じて生きていく存在だと思うのです。本願力なんて当てにならない、やはり軍事力だと言うのであれば、その人は本願を信じていないのであって念仏者ではないと思います。軍事力ではなく本願を信じて生きていくのが念仏者である。そういうことではないかと思うのです。
<非戦・非武装に立つ平和構築>
私は、軍事力を頼りにせず、ただ本願のみを恃み、「非戦・非武装」に立ち続けるのが念仏者の平和運動だと思っています。日常のあらゆる場面で、戦争と軍事力のない、全てのいのちが共に生きることができるような世界を願い求めて、日々の行いを積み重ねて生きていくこと。これが念仏者に願われていることだと思うのです。まさにそれが、阿弥陀さまから私たちがいただいているお仕事だと思うのです。
「非戦・非武装」の日本国憲法の下にある日本政府も、いたずらにアメリカに追随するのではなく、自衛隊を徐々に縮小して災害救助隊に転換するなどし、在日米軍基地も徐々に縮小していって、日本の非軍事化を進めていく。そして、東アジアに国際平和を構築するための国際的なシステムをつくり上げていく。そのような外交努力をしていくべきだと思うのです。そして私たちは主権者として、そのような政府を実現していかなければならないと思います。そもそも日本は、資源もなければ食料もないような国です。こんな国を占領しても、何の得にもなりません。日本への侵攻・領有を「失った領土の回復」として正当化できる国もありません。私は、日本が非戦・非武装で平和外交を積極的に進めていけば、日本が侵攻される危険性はまずないと思うのです。
<非暴力・不服従抵抗による市民的防衛>
しかし「非戦・非武装」と言いますと、「万一とんでもない指導者がいて、日本を攻撃してきたらいったいどうするのだ。手を上げて降参するのか。あなたたちの頭の中はお気楽なお花畑だ」と言う人もあります。私はその心配はないと思っていますけれども、その疑念、揶揄に対する回答は一応持っていた方が良いと思います。私が持っている回答は「非暴力・不服従抵抗による防衛」です。平和学では「市民的防衛」と言われます。私たちはそれを追求していくべきではないかと考えています。仏教の基本にあるのは「非暴力」です。私たちが攻撃された場合でも非暴力で対応すべきだと思います。暴力は使わない。しかし相手の言うことは一切聞かない。万一外国の軍隊が入ってきてあれこれ指示しても言うことを聞かない。自分たちの考えに従って今まで通りの自分たちの生活を続けていく。それが「不服従」です。
非暴力というと無抵抗というように捉えられることが多いですが、非暴力は決して無抵抗ではありません。「不服従抵抗」という抵抗の仕方があります。非暴力・不服従抵抗は、国内で政府が不法・不当なことをしてきた時に、それに抵抗するために行われることが多いのですが、外国からの侵攻・占領・支配に対する抵抗として行われた例は少なくありません。最近は非暴力・不服従抵抗のやり方もいろいろと研究をされてきていて、研究によれば、抵抗の仕方として198通りのやり方があるとされています。ボイコット、ストライキ、座り込み、集団移住というようなものがその中に含まれています。
(『真宗』2024年6月号 東本願寺出版発行
念仏者の「非戦・非武装」に立つ平和運動 より引用しました)
2024年10月23日
今日も快晴!? 2024年10月

9月に豊田大橋の下で行われた「橋の下音楽祭」の関連イベントで、元イスラエル空軍兵のダニー・ネフセタイさんの「どうして戦争しちゃいけないの?」と題する講演会がありました。1957年にイスラエルで生まれたダニーさんは、兵役のある国で、「国のために死ぬのは素晴らしい」、「夢は空軍パイロット」と当然のように思いながら育ちました。高校卒業後、空軍に入り戦闘機に乗るための訓練を受けましたが、残念ながら実技試験の終盤を突破できず、パイロットにはなれませんでした。除隊後、世界各地を放浪し、22歳で日本に来てから様々な気づきがあったと言います。以下、講演の最中、メモを取った部分を紹介します。
「自分は、パイロットになれなくてラッキーだった。なぜなら、戦闘機の目的はたった2つ。人を殺すことと、物を壊すこと。自分はパイロットになれなかったおかげで、人を殺さずに済んだ。」
「軍隊の成り立ちは、①差別・・・良い側と悪い側に分けないと、相手を殺せない。②人間をランク付けし、命令に従う。③解決方法は武力のみ。」
「戦争は、始まると歯止めがきかない。人間は、鉄の力に酔ってしまう。楽しくなっちゃう。1937年の南京事件も、だんだん楽しくなってきて、もっとやろう、もっとやろうとエスカレートした。」
「イスラエルでブルドーザー部隊で従軍した人は、イスラエルに戻り、PTSDを発症している。国は、一人の健康な人間と一人のメンタルが病んだ人間を抱える。これでは国が成り立たない。」
「戦争では、儲かる産業と儲かる国がある。アメリカは救援物資と同時に武器の両方を供給する。」
「憎しみは憎しみを生み、次の犠牲者が生まれる。80年前、大東亜戦争の最中、戦争で戦った自分は英雄であり、天皇を守り、国を守ったと考えていた。しかし、国に帰り、冷静に自分のやったことを考える(と、良心の呵責に耐えられない)」
「政治家の間違った判断、洗脳とプロパガンダ(が戦争を生む)。軍人が殺すのは、敵ではなく人間。」
「敵に攻められないよう、抑止力として武器が必要と言うが、ロシアとウクライナの戦争を見ても、核兵器を持っていても戦争は始まった。何の抑止力にもならない事は明らか。日本がどんなに武器を持ったとしても、中国が日本を襲おうと思えば襲う。中国は日本の4倍の軍事費があり、10倍の軍隊がある。実際に戦争が始まったらどうしようもない。自衛隊には何の意味も無い。だから、戦争にならないように、始まる前になんとかしないといけない。」
「私たちは、歴史を学ぶが、歴史から学ばない」
「戦争に燃費は関係無い。環境に良い戦争や戦闘機はない。戦車の燃費は、1Lで300m。F35戦闘機(ブルーインパルス)は、1時間飛ばすのに5600Lのガソリンが必要。これは、車1800台分。1時間飛ばすのに、600万円掛かる。そして、環境を汚す。そんな戦闘機を、日本は米国から147台購入予定。」
ダニーさんは、「世界に先駆けて戦争を放棄する平和憲法を持った日本が、戦争の準備を始める始末」と嘆きます。「人権を尊重すること、想像力と心を使うこと。「敵」にも幸せになる権利があると気づくこと。実際に戦争に反対する世界を望むなら、批判の声を上げること。それも、控え目にではなく、大きな声を上げる必要がある。」
私のこの拙い文章も、もちろん「戦争反対」の声ではありますが、まだまだ小さく控え目だと感じます。講演会で購入したダニーさんの著書『国のために死ぬのはすばらしい?』『イスラエル軍元兵士が語る非戦論』を読み、私なりの大きな声の上げ方を考えたいと思います。
2024年10月23日
清風 2024年9月

和をもって 尊しとなす
十七条憲法 第一条より(聖徳太子制定)
憲法第九条は日本の戦争責任告白です。
歴史小説家の司馬遼太郎は、昭和20(1945)年当時、関東平野を守るべく栃木県佐野の戦車第1連隊に所属していました。そこで大本営から来た少佐参謀の言葉に驚愕します。
連隊のある将校が、この人に質問した。
「われわれの連隊は、敵が上陸すると同時に南下して敵を水際で撃滅する任務を持っているが、しかし、敵上陸とともに、東京都の避難民が荷車に家財を積んで北上してくるであろうから、当然、街道の交通混雑が予想される。こういう場合、我が80両の中戦車は、戦場到着までに立ち往生してしまう。どうすればよいか。」
高級な戦術論ではなく、ごく常識的な質問である。だから大本営少佐参謀もごく当たり前な表情で答えた。
「轢き殺してゆく。」
『歴史の中の日本』中公文庫 1994年刊 P311~312
こうした体験から、司馬遼太郎は別の随筆で次のように論評しています。
戦争遂行という至上目的もしくは至高思想が全面に出てくると、むしろ日本人を殺すということが、論理的に正しくなるのである。(中略)沖縄戦において県民が軍隊に虐殺されたというのも、よく言われているように、あれが沖縄における特殊状況だったと、どうにも思えないのである。
『歴史と視点 ― 私の雑記帖』新潮文庫 1980年刊 P90
自衛官出身の軍事専門家、潮 匡人さんは
軍隊は何を守るのかと言い換えるなら、その答えは国民の生命・財産ではありません。それを守るのは警察や消防の仕事であって、軍隊の「本来任務」ではないのです。
『常識としての軍事学』中公新書ラクレ 2005年 P188
こうした軍事専門家の発言は現実を踏まえた道理であり、虚偽を並べ立てる政治家よりもよほど信頼できるものと考えられます。
かつてドイツのメルケル首相は、日本訪問の折、当時首相であった安倍首相と対談し、「日本はアジアに友人がいますか」と問われたそうです。その発言には次のような背景があります。
ドイツは敗戦後、隣国フランス・ポーランドと友好関係を深める努力をしてきたことを説明されました。ナチスによるユダヤ人虐殺などをめぐって、ヴァイツゼッカー大統領は第2次世界大戦敗戦40周年にあたりドイツ連邦議会で演説を行い(1984年5月8日)、
問題は過去を克服することではありません。左様なことができるわけではありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです。
『荒れ野の40年』岩波ブックレット№55 1986年2月20日 岩波書店刊
と述べています。ドイツは敗戦の日・5月8日にフランスとポーランドへ、大統領並びに首相が慰霊に訪れているのです。
日本は第2次大戦で、アジアの国々に攻め入ってたくさんの軍人・市民を殺戮しているにもかかわらず、次の世代まで謝らせるわけにはいかないとし、「おこらなかったこと」にしてしまっていると言われています。
戦後80年、そろそろ今の日本政府も、まず沖縄の米軍基地の管理権を日本に返却させる交渉を始めるべきではないでしょうか。ドイツ・イタリア・フィリピンの戦後の歩みに学び、独立国としての体制を整えるべきだと思うのですが。
日本がアジアの一員として存在し続けるためには、大陸や朝鮮半島の国々と協力関係を築き、アジアにおける集団安全保障の枠組みをいかに作っていくかという議論をする時期にきているのではないでしょうか。憲法第9条は、こうした信頼関係を結ぶ上で、軍事力強化によってではなく、安心の供与という点から、重要なものだと思われます。
百年以上にわたり悲惨な戦争を繰り返してきたドイツとフランスが、今後軍事的に衝突を繰り返すと考える人はほとんどいないでしょう。1963年に締結されたエリゼ条約締結50周年(2013年1月)にあたり、駐日独仏大使が連名で発表した寄稿文(朝日新聞2013年1月13日付)で、「対立がもたらす代償がいかに大きく、和解から得られる利点がいかに大きいかを、歴史の教訓から知った」として、今後の平和的独仏関係を確認しています。
註)今月号の「清風」紙の「今月の掲示板」に紹介されている「運命の花びら」
(森村誠一)、また先月号・今月号の「守綱寺カレンダー」“本堂に座って”に
掲載されている平川宗信氏の文章も、ぜひお読みください。
2024年10月23日
お庫裡から 2024年9月

暑い暑いと言い暮らしているのに、ふっと見上げた空には羊雲が。ああ、確実に季節は移ろっていると知らされる。
お盆の帰省を楽しみに待っていた東京の孫達(小2のの葉、年長さち)。やっと顔を合わせても、そうおばあちゃん、おばあちゃんと寄ってこない。我が家には私より若くて元気なお兄ちゃん(誓)お姉ちゃん(在)がいる。2人もよく小さい子の面倒を見て微笑ましい。
それもつかの間、この帰省に合わせて父方の高齢のひいおばあちゃんに会わせておきたいと、わずか2日でそそくさとそちらに向かった。
ちょっとずれて開くんも帰省。「ロボコン見たよ」「ちゃんと食事は取ってる?」もう後は何を喋っていいのかわからない。なのに誓くんとはずーっと喋りっぱなし。よく会話の種の尽きぬものだと感心する。会話の中身はわからなくとも、兄弟が仲良くしているのは見ていてうれしい。
お盆が過ぎたら、彼もさっさと東京に帰ってしまった。
お盆の前は、東京のあの子たちが帰ってきたらと、心積もりというか備えというかあれこれ考えていたのに、何もしてやれないうちに、みんな「お母さん無理しないでね」「熱中症に気をつけてね」等、労りの言葉を残して帰っていった。
もう私は子や孫に何かをしてやれることはないのだ。高齢者の私は、以後、私を生き切ることに徹しなければならない。「御教えのままに生きるものこそいのちの運命のいたずらに打ち勝つ者である(九条武子)」御教えのままとは、私の前にやって来たご縁の出来事を受け止め、そこをどう生きるかと問われることだといただきます。
今朝もまた覚めて目が見え手も動く、ああありがたし、今日のいのちよ。(平沢 興)
高齢者になっても学ばねばならぬもの、磨かねばならぬもののあるのはありがたいことだ。南無阿弥陀仏。
2024年10月23日
今月の掲示板 2024年9月

寝ている人の目を覚ますのは易しいが
目を開けて寝ている人の目を覚ますのは
難しい(物種吉兵衛)
忘れてならないのは
いついかなる時も
なぜ心は喜んでいるのか
悲しんでいるのか
怒っているのかということを
考え続けることだ(森村誠一)
自分の観察者、考察者たる
自分を育てておくのだ(森村誠一)
食べものはめぐっている
人間は
その一部に過ぎないという
自覚が必要だ(絶筆 野坂昭如より)
嘘は
百年かけて固めましても
嘘です(平野 修)
利潤穢土(浅田正作)
人間が利潤を追いすぎ
自然のバランスを崩すとき
地には害おおく
山に災おこるという
はてしもなく利潤を追えば
いつかここは 穢土
特定秘密保護法の成立
国益を守るために必要だというこの法
国益とはいったい何なのか
少なくとも国民の側に立っての
益でないことははっきりしている
(2013.12だまし庵日記 野坂昭如)
「政治を信用している人なんていないよ。
政治権力は常に不信の上に成立している。」
「だから政治に無関心になるのかな。
しかし、全国民が無関心になったら怖いね。
ふっと気づいた。
ヒットラーやスターリンに支配されているのと
何ら変わらない。」
「政治はいつも疑惑と警戒の目で
監視している必要があるな。」
(「運命の花びら」森村誠一著より)
2024年10月23日
本堂に座って 2024年9月

今月も先月に引き続き平川宗信先生の講演録を紹介します。今回は、日本の現状から軍拡、有事の際の対応についてのお話です。
<今の日本は「新しい戦前」>
このような本願の願い、憲法の理念・条規から見ていきますと、今の日本の現状は、非常に危うい、危機的な状況にあるように思えます。私は、現状に極めて強い危機感を持っています。最近、「新しい戦前」という言葉があちこちで聞かれるようになってきています。今の日本は、戦争準備が進んで、足早に戦争に向かっている。私は、そんな思いがしてなりません。
本願も憲法九条も非戦・非武装を願っていますが、それとは真逆の動きが、現在、急速に進められていると言っていいと思います。その意味で、日本はアメリカと一体になって軍事大国、戦争をする国へと向かっていると思えてならないのです。
しかし世論調査を見ますと、かなりの国民がこれを容認しているように見えます。それはなぜかと考えますと、おそらく一つには「台湾有事は日本有事」と言われて、そこに危機感を感じているということがあると思います。そして、もう一つには、ウクライナ戦争を見て、強力な軍事力を持たないと外国に侵攻される、軍備は強化しなければならないという意識が、国民の間にかなり広まってきていることがあるのではないかと思います。
<安全保障のジレンマ>
平和学では、「安全保障のジレンマ」ということが言われます。どういうことかと言いますと、ある国が他国 ―「仮想敵国」ですね ― を念頭に軍備を増強したとします。そうすると、相手の国もそれを見て、「向こうは軍備を増強した。このままでは自分たちが負けてしまう」と、軍備を増強します。そうすると、こちらの国も、「向こうはまた軍備を増強している、こちらも」と、さらに軍備を増強し、軍拡競争になっていきます。それでは軍拡競争が無限にできるかと言えば、そんなことはないわけです。兵士にできる人員にも財政にも限界がありますから、無限に軍備を増強していけば、国は破綻してしまいます。そして、両方の国が軍備を拡大していけば、双方の軍隊が交錯して接触する機会が増えて、偶発的な軍事衝突が起きて戦争になる可能性が大きくなります。軍事力で平和を維持しようとすると、軍拡競争になって国が破綻するか、さもなければ軍事衝突によって戦争に発展するか。いわば、二つの落とし穴に落ちていくことになります。これが「安全保障のジレンマ」です。
軍事力によって国を守ろう、平和を維持しようとしても、うまくはいきません。これが最近の平和学の知見です。その意味で、日本が軍備増強、軍拡によって平和を維持しようと考えるのは、危険だと思います。特に、中国と軍拡競争をやるのは無謀だと思っています。私は、日本という国は、もともと戦争ができるような国ではないと思っています。兵器も資源も燃料も食料も、すべて輸入に頼っている国です。自給できないわけです。もし戦争になって海上輸送が途絶えてしまえば、日本は干上がってしまいます。まず真っ先に食料がなくなってしまいます。「腹が減っては戦はできない」のでありまして、日本は戦争ができない国なのです。
それに、そもそも戦時に軍隊は国民・住民を守りません。これは沖縄戦で沖縄の人たちが嫌というほど思い知らされたことです。軍隊がいれば攻撃対象になるだけであって、軍隊は住民を守ってはくれないというのが、沖縄戦の教訓です。法律上も、自衛隊は「住民を守る、国民を守る」とはされていません。自衛隊の任務を定めた自衛隊法第三条には、「我が国を防衛すること」が「主たる任務」として書かれていて、国民・住民を守ることは任務として書かれていません。国を守ることが、自衛隊の任務なのです。
では有事の際、住民、国民を守るのはいったい誰なのか。これは有事法制によって、自治体の責務とされています。有事の際に住民を守る責任を負っているのは、自治体です。しかし有事の際、ミサイルが飛んできたり砲弾が飛んできたりしている中で、自治体が住民を守れるか、保護できるかといえば、できるはずがないと思います。有事になったら、住民の逃げ場はない。私はそのように思っています。
(『真宗』2024年6月号 東本願寺出版発行
念仏者の「非戦・非武装」に立つ平和運動 より引用しました)
2024年10月23日
今日も快晴!? 2024年9月

お寺友達から、『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』(しんめいP著。鎌田東二監修。サンクチュアリ出版)という本を紹介されました。著者のしんめいPさんのプロフィール、「東大を卒業して大手IT企業に就職するも、仕事が出来なくて退職。鹿児島県にある島に移住して教育事業をするも、人間関係が上手くいかず退職。一発逆転を狙って芸人としてR-1グランプリ優勝を目指すも、一回戦敗退。結婚、離婚を経て無職になり、実家で引きこもっていたとき、東洋哲学に出会う」という部分を読んだだけで(何それ!気になる!)と思いましたが、ブッダから始まり、インドから中国、日本と伝わってきた仏教界の著名な方とその思想を紹介する「哲学エッセイ」は、軽く面白く分かりやすく、浄土真宗の教えを開かれた親鸞聖人については次のように紹介されています(前半部分のみ一部抜粋)。
「仏教の哲学は、インド→中国→日本に伝わった。そして、日本で破壊的な進化を遂げたのだ。どれくらい破壊的に変化したか?クラシック音楽がヒップホップになるくらい。ブッダもびっくり超進化なのだ。親鸞を紹介する。800年くらい前の、平安の人だ。クラシック仏教をヒップホップにしてしまった人物である。どういうことか?仏教にはたくさんの「宗派」がある。「空」という目的地を目指すうえで、色んな交通手段がある。この交通手段の違いが「宗派」と思って貰えば良い。親鸞は「浄土真宗」を作った。浄土真宗では、どうやって「空」の境地に行くのか?徒歩か?電車か?飛行機か?実は、そんなレベルじゃない。「空」の方がこっちに来る。逆にね。いや、そんなことある?親鸞の哲学は、最高にとがっているのだ。」・・・「実は、親鸞はエリートだった。そもそも、当時、お坊さんはエリートなのだ。・・・天皇も仏教を守っていた。権力もすごかった。親鸞は、そんな仏教界の頂点、「比叡山」にいた。・・・しかし、親鸞にはたえられないことがあった。当時の比叡山は腐っていたのだ。・・・比叡山は、政治権力と完全にべったりだった。お坊さんたちが、金とポストの争いにあけくれていた。誰も真面目に仏教をやっていない。そして、比叡山の外では人々が地獄のように苦しんでいた。親鸞のいた平安末期の京都は、日本の歴史上最悪の時代である。なんと、戦争、感染症、大飢餓、大地震、大火事、みんな起きた。この世の地獄のフルコースである。」「親鸞は悩んだ。まさにこの世の地獄で人々が苦しんでいる。でも、自分はエリートでぬくぬく生きている。仏教って、人を救うためにあるんじゃないのか?親鸞は純粋だったので、この矛盾にたえられなかった。そして決断した。比叡山を下りる。エリート街道を捨てて、まちで、仏教の力で人々を救うんや。」・・・「親鸞は、比叡山で20年間めちゃくちゃ勉強して、めちゃくちゃ修行していた。自分なら、人のために出来ることはあるはず、と思っていた。しかし、現実は甘くなかった。・・・とにかくみんなメシが欲しい。座禅や瞑想なんて「意識高い系」過ぎて、受け入れられるはずが無かった。親鸞は、自分の無力さに絶望した。・・・悩みに悩んだ絶望の先に、希望の光を見出した。仏教をひっくり返すような大逆転の哲学にたどりつく。それが「他力」の哲学なのだ。」
昔日本史の教科書で習って一覧表にして必死に憶えた「宗派・・・浄土真宗。開祖・・・親鸞。主要著書・・・教行信証。中心寺院・・・本願寺」よりは、ぐっと身近に感じられる気がします。