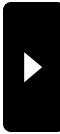2023年06月16日
清風 2023年6月

仏教は
「人間奪還の教え」
である
高光大船(1897~1951)清沢満之に師事
暁烏敏・藤原鉄乗・師で、加賀の三羽烏と言われている。
現代は、「宗教」という言葉自体を吟味しなければならなくなっている時代と言えます。親鸞聖人は比叡山を下って法然上人に出会われ、その感激を『教行信証』に執筆され、その内容を同書「後序」において「真宗の詮を鈔し、浄土の要を?う」と述べておられます。
「真宗」との名告りについて、この2、3年の「清風」巻頭で紹介してきた文を参考にしつつ、宗教について共に考えたいと思います。
人間の本質はGDP(国民総生産額)によって計られうるものではない。我々は「学びの社会」に入ったということをしばしば耳にする。これは確かに、真実であることを希望しよう。 (『人間復興の経済』佑学社刊 P14上段L10)
シュマッハー(1911~1977)
シュマッハーは次のように述べた後、続いてガンジーの言葉を引用しています。
経済的観点からすれば、人間の英知の中心的概念は永続性である。我々は永続性の経済学を研究しなければならない。長期にわたる継続が不条理に陥ることなく確保されるのでなければ、なんら経済的な意味はなさない。限定された目標に向かっての“成長”はありうる。しかし、無制限に一般化される成長はありえない。
(同書P24上段L11~下段L1)
地球はすべての人間の必要を満たすのに十分なものを提供するが、すべての貪欲を満たすほどのものは提供しない。 (同書P24下段L2)
ガンジーの言葉(貪欲は「欲望」と理解すべきであろう。)
このガンジーの言葉について、「生命科学」に代わり「生命誌」という名のもとで研究をしておられる中村桂子さんの提言を、次に紹介します。
“科学”から“誌”への移行にどんな意味があるのか、この生命誌から生きものやヒトについてどんなことがわかるのか、それが、自然・人間・人工の関係づくりにどうつながっていくのか。そこからどんな社会がつくれるのか。ヨチヨチ歩きを始めたところですので、スパッと答えは出ませんが、一緒に考えていただくための素材を提供したいと思います。
(『生命誌の世界-私たちはどこから来て どこへ行くのか-』
NHK教育テレビ講座テキスト 1999年4月~6月)
中村桂子(1936~)前生命誌研究館長
「人間は生きものであり、自然の中にいる。」これから考えることの基盤はここにあります。これは誰もがわかっていることであり、決して新しい指摘ではありません。しかし、現代社会はこれを基盤にしてでき上がってはいません。そこに問題があると思い、あらためてこの当たり前のことを確認することから出発したいと思います。
まず、私たちの日常生活は、生きものであることを実感するものになっているでしょうか。朝気持ちよく目覚め、朝日を浴び、新鮮な空気を体内にとり込み、朝食をおいしくいただき……これが生きものの暮らしです。目覚まし時計で起こされ、お日さまや空気を感じることなどまったくなしに腕時計を眺めながら家を飛び出す……実際にはこんな朝を過ごすのが、現代社会の、とくに都会での生活です。ビルや地下街など、終日人工照明の中で暮らすのが現代人の日常です。これでは、生きものであるという感覚は持てません。(略)そこで、ここでの提案は、まずは一人ひとりが「自分は生きものである」という感覚を持つことから始め、その視点から近代文明を転換する切り口を見つけ、少しずつ生き方を変え社会を変えていきませんかということです。一人ひとりの気持ちが変わらないまま、例えばエネルギーだけを脱原発、自然エネルギーに転換と唱えても今すぐの実現は難しいでしょう。しかもそれはあまり意味がありません。自然エネルギーを活用する「暮らし方」が大切なのであり、その基本が「生きものである」という意味なのです。
(『科学者が人間であること』中村桂子著 岩波新書 第6刷 2018年発行)
2023年06月16日
お庫裡から 2023年6月

今年も早や折り返しの月を迎えました。
自分ではしっかりしているつもりでも、つもりはやはり、思い込みに過ぎないと知らされる出来事がありました。
冬に枇杷の花が咲いているのを見つけ、よーし今年こそ鵯に食べられぬよう袋がけしようと思いました。
5月初め、松平JAへ花苗を買いに行った時、そこで枇杷を包む袋が売られているのを見つけました。「よーし、やった。これで今年は美味しい枇杷が食べられるぞ」ワクワクして、1包み(30枚入り)でいいものを、失敗するかもしれないと2包みも買いました。準備万端。
いよいよ実が大きくなりだし、そろそろ袋がけしようと思ったら、あの買った枇杷袋がないのです。オレンジ色をしていたので、そう見落とすはずはないと思うし、目立つようにと何かに立てかけたという記憶はあるのです。それがない。もう一週間以上探しています。立てかけたというのは思い込みで、机の上の新聞や広告と一緒に出してしまったのかもしれません。たぶんそうなんでしょう、あーあ。
最近、一日に2つ以上の用事をこなそうとしているのに、1つを忘れる事が頻発。これは私の気の散漫によるものなのか、老人性の呆けというものなのか。
日常の用事は忘れてもそれだけのことだけど、私はこの世に何をしに来たのか、という大きな課題(後生の一大事)が、我が身から我が思いを破って、現実にうなずき、そこに立たしめてくれる。
2023年06月16日
今月の掲示板 2023年6月

物質の豊かさが
そのまま
人間を豊かにしない
身の周りの状況と、心の満足・不満足は
一体であるように思いがちだが、違う。
はっきり独立している。
人間の心は
物質という周りのものに
大変影響を受け易いけれど
しかし、はっきりと独立している
いれもの 浅田正作
やどかりが
自分の殻を
自分だと言ったら
おかしいだろう
私は自分の殻を
自分だと思っている
せっかくいただいたこの身(人間)
傷つけたり、傷めたり
愚痴ったりするのは
他ならぬ 私の心です
先ずもって、助からねばならぬのは
この心です
寿命に対して
安んじてその寿命を生きていく
これが、本来の世界
この生命にすら
意味があるか
価値があるか
という対象になり
例い、生命として寿命があっても
生きられないという状況が
生じてきた
鏡 浅田正作
毎朝 毎朝
洗面所の鏡にむかって
私は 自分のなにを
見ていたのだろうか
2023年06月10日
本堂に座って 2023年6月

JAF(日本自動車連盟)から発行されている機関誌『JAF Mate』には、「幸せって何だろう」というテーマの連載があります。
毎回、さまざまな分野の方がご自身の“幸せ”についての考え方・日々の生活で感じる“幸せ”について書いておられます。
たまたま目にした小山薫堂さんの文章を紹介します。
幸せの閾値(いきち)
子供の頃、ゴーカートが大好きだった。ある日曜日、父親の運転で遊園地に向かう車内での出来事。
渋滞に巻き込まれて疲れ切った表情でハンドルを握る父親に、8歳の僕は熊本弁でこう言った。
「これからゴーカートに乗るとに、どうしてそぎゃんつまらん顔ばしとっと? 嬉しくなかとね?」
すると父親は冷静にこう返してきた。
「お父さんはな、ゴーカートよりも速く走れる車ばここまで運転して来たとよ。だからもうこれ以上、運転はせんでよか。ゴーカートには乗らんけんね」
何てつまらない人間だろう、とその時は思った。
ゴーカートに乗る……それは8歳の自分にとって最高に幸せな時間だった。
「閾値」(いきち)という言葉をご存じだろうか? 簡単に言うと「刺激を感じる境目となる値」を意味する学術用語である。
嗅覚の閾値を例にしてみよう。
ニンニクを臭いと感じるのは、閾値を超えるから。
その瞬間、ニンニクを臭いと感じる閾値は上昇するらしい。
よってニンニクを食べた本人はその臭さをあまり感じなくなる。食べていない人がそこに来ると、すごく臭いと感じるのは、閾値が正常のままだから。
それと同様に幸せにも閾値がある、と僕は思っている。
子供の頃はゴーカートに乗るだけで幸せを感じるのに、大人になると本物の車でなければ幸せを感じなくなる。
それは明らかに、幸せの閾値が上がったからだ。最初はどんな車でもワクワクしていたはずなのに、徐々にもっといい車が欲しくなっていくのも、閾値が吊り上がっていくからに他ならない。
自分の幸せの閾値を保つ、もしくは下げる! それこそが、自分が常に幸せでいられる秘訣だと思う。
あらゆる閾値が低かった子供の頃の幸せを思い返してみると、実は今の自分が手に入れられる幸せがまだまだたくさん存在していることに気づく。幸せは探し求めるものではなく、気づくものなのだ。
先日、84歳になった父親から久しぶりに電話がきた。免許を返納することにしたと言う。
その声はとても淋しそうだった。50年ぶりに父親とゴーカートに乗りに行くのも悪くないと思った。
(『JAF Mate』2022年夏号 JAFメディアワークス発行より引用しました)
初めのうちは「幸せ」と感じていたことが、いつしか当たり前になって(=閾値が上がって)しまって、幸せを感じられなくなってしまう…。
小山さんの「幸せは探し求めるものではなく、気づくもの」という指摘は、私たちの日常を見事に言い当ててくださっています。
“幸せの閾値”を確かめてみると、日常の中に気づかずにいた「幸せ」をたくさん見つけられるのだと思います。
2023年06月10日
今日も快晴!? 2023年6月

GWの事です。東京で下宿をしている長男から、「顔の左半分が麻痺して、上手く目が閉じないし口も閉じない」と連絡が来ました。
顔面麻痺とはただならぬ状況です。
3日に帰省してくる予定ではありましたが、1日&2日と大学の授業があったので、とりあえず大学の保健センターに駆け込んだところ、「紹介状を書くから、提携している大学病院に行きなさい。」と言われたようです。
しかし「大学病院も新規で一番早く予約が取れるのは6日(土)。どの病院も混んでいるし、とりあえず3日にそちらに帰る。」と言います。
しかし、豊田に帰省したところで医療機関は休みだし、どうしたものかと東京に住む妹たちにも相談したところ、「私も帯状疱疹になって、しばらく放置したら大変だった。すぐに病院に行った方が良い。早ければ早い方が良いよ!」と、妹から長男にも直接電話を入れてくれて、「1日と2日の平日なら見て貰えるはずだから、とにかくどこでもいいから空いている病院に行くように!」と、勧めてくれました。
幸い大学の最寄りの駅周辺に4月に開院したばかりの耳鼻科の病院が見つかり、連絡を入れてみたところ、「今来れば、患者さんは誰もいないからすぐに診られますよ」と言ってもらえたので、そちらに飛び込み、必要な薬は処方して貰えました。
原因としては、帯状疱疹と同じで、元々身体の中にいる弱いウィルスだけど、免疫が下がっているときに出てきて悪さをするウィルスにやられたようでした。
大学でロボコンサークルに入った長男は、理系の実験などの授業の忙しさに加えて、ロボットの設計、ロボコンにエントリーするための書類作り、新入生歓迎会用の資料作り等々…、かなり忙しい生活を送っていたようでした。
「朝の9時から夜の9時までずっと大学にいる」、「土日もずっと大学にいる」、「やらなければいけないその日の課題を終わらせたら、もう夜中」、「昼ご飯も食べる暇が無くて、一日1食」、「何時に終わるか分からない実験の授業があり、一度でも休んだら単位が貰えない。
終わる時間も読めないから、バイトも出来ない」等々、悲惨な生活を送っているようでした。
身体を壊したらどうするの?ほどほどにしなさい、休みなさい、食べなさい、等々…。
言いたいことは山のようにありますが、自分の学生時代を振り返ってみると、(そういえば、人のことは言えないなぁ…)と思います。
授業に部活にサークルにバイトと一日予定はパンパンで、寝る間も惜しんで遊び、徹夜明けでバイトに出掛けたり、身体の事なんて全く考えていませんでした。
何かあっても、離れて暮らす親を頼るのではなく、大学の友人やサークルの仲間、寮の先輩たちを頼りに、なんとか乗り切って来たのでした。
若さで大概のことはなんとかなりました。
間違いなく「青春」と呼べるあの時代があったからこそ、その後の仕事や子育てと言った思い通りにならないことばかりの時期も、柔軟にやり過ごすことが出来ました。
今、長男は青春まっただ中にいるのです。
やりたいことを、やりたいだけやればいい。
「母親の役割は、母親がいかに役に立たないかを子どもに教えること」だと思っているのですが、子どもを信頼し、任せておけば、大抵のことは自分の力でちゃんと解決していってくれます。
長男が冬に高熱を出して寝込んだときも、「大学の友達がポカリを差し入れしてくれて、なんとかなった」と後から聞きました。
何かあった時も、自分から周囲に「助けて」と言うことが出来れば、とりあえずは大丈夫かなと思います。
晴れて今年のNHKロボコンに出場が決まった様ですので、テレビで応援したいと思います。
2023年06月10日
清風 2023年5月

なりたい自分にならなくとも
なった自分で生きたらいい
山田ルイ53世(漫才コンビ髭男爵)
朝日新聞(2020.4.1)「折々の言葉」より
人生を生きるにあたって 清沢満之
先ず、死後のことは不明であり、生前(生まれる前)についても不明である。
それでは、自己(僕、あるいは私)とは何ぞや。(以上意訳)
是人世の根本的問題なり。
自己とは他なし。絶対無限の妙用に乗託して、任運に法爾に此の境遇に落在せるもの、乃ち是なり。(『臘扇記』清沢満之 著)
5月、月日の経つのは速いといいますが、年を取ると、特にそのようです。
もう桜も散って、緑一面の初夏の候となっています。
そんな時に、たまたま、境内の掲示伝道の一つに、先に掲げた言葉を思い出しました。
4月・5月は新しい出発というか、入学試験も終って、学生また社会人として、上の言葉にあるように、入学・入社し戸惑っておる人など、ま、いろいろあるのではないかと思います。
話は少し飛びますが、GNPとGNHという言葉について、ご存じでしょうか。GNPは国民総生産高を表わします。
現代では、国力というものを1年以内に生産した生産物の集計値で表します。GNPの大きい国、例えばG7(先進7ヶ国の略)など、経済的に豊かな国が先進国といわれています。
GNHは「国民総幸福度」を現わす言葉で、ブータン国王の提唱した、ブータンの国の目標を示す言葉として注目を集めています。
さてGNPですが、こちらのほうは、今、我が国では大学も理科系学部出身者が引っ張りだこなのも、半導体を部品として使用する製品が増え、GNPの視点から、この半導体の生産、そして半導体を使う自動化製品が増加傾向にあり、理科系の人材を要求する企業が増加しているから、と言われています。
GNPは必ずしも国民の生活の充実度を示すものではないと言われているのですが、しかし世界は今や、決定的にテクノロジー(科学・技術)に支えられた自由で高度な消費享楽生活を志向していると言えます。
上記に上げた「半導体」こそ、そのテクノロジーを支えている製品です。しかし、アメリカを筆頭に自由主義陣営が、この10年間ほどで、分断国家の状況を示しつつあるのは何故なのでしょう。
これは、人間の健康な面を表わしているとはいえないでしょうか。
それは、どういうことか― 人間は美食して好きにふるまうために、この世に浮かれてきたわけではないのです。
それなら、お釈迦様はマカダ国の皇太子だったのであり、出家の必要はなかったのです。また豊臣秀吉は、一介の平民の出自でありながら太閤にまで出世したのですが、辞世の歌として伝えられているのは
露と落ち 露と消へにし わが身かな なにわのことも 夢の又夢
でした。
今、我々現代人が生きる唯一の目標・GNPという目標は、この社会はたんなる環境破壊でも資源枯渇でもなく、「心の荒野」に向かっていることを現わしていると言えるでしょう。
つまり、今、問われているのは、釈尊が
あなたは あなたで 在ればよい。
あなたは あなたに成ればよい。
と呼びかけて下さっているように、「私が生きる」「生きている」ということが、つまり私に与えられている「いのち」が、私に何を要求しているかをはっきりさせなさいということではないでしょうか。
我々は問われている存在なのだ、ということを忘れさせられてしまっているのです。「美食をして好きに振舞うために、君は生きていくのか」と。
その結果が、半導体を必要とする、人間の要求である生活の豊かさ・快適さを望む欲望であり、結局、人間の道具化・モノ化をも推進させるのであって、「存在の一切の意味を無化する」虚無の遊動に対して開かれた文明であり、その行く先は「心の荒野」でしかないのでしょう。
「人間は絶対無限を追求せずしては満足を得ることができない」のです。
「地球はすべての人間の必要を満たすのに十分なものを提供するが、全ての人間の貧欲を満たすほどのものは提供しない」(シュマッハー『人間復興の経済』佑学社刊 P24下段L2・『スモール イズ ビューテイフル』講談社学術文庫P43L4)とも言われます。
では、「絶対無限を追求する」とはどういうことでしょう。
Posted by 守綱寺 at
10:53
│Comments(0)
2023年06月10日
お庫裡から 2023年5月

新学期が始まりました。
高校生になった在ちゃん、大学生の誓くん、2人共に毎日が新しい体験の連続です。
夕食の時間は2人の体験報告会です。
在ちゃんは「高校は中学とは全然違うー」と、毎日興奮気味。「先生があれこれ」「クラスメートがあれこれ」「今日は○○があって、あれこれ」「お弁当の時間にあれこれ」話し出したら止まることがありません。
誓くんは、時々手を挙げて「僕にも話させてくれん」と、在ちゃんの話の中に割り込みます。
「八事駅の乗り換えで、名城線が満員で乗り込めず、一台遅らせたら、一限目に走って走ってギリギリ間に合った」とか、「歩いていたら南山大学に出たので、知ってる人がいるかなーって学内を歩いていたら、本当に知ってる人がいた」とか「学食に行ったら棚はほとんど空っぽで、やっと最後の一つにありついた」とか、こちらもおもしろい話ばかりで、今日は2人からどんな話を聞かせてもらえるのか、毎日の夕食時が楽しみです。
しかし、こんな時間もそのうちに、こちらが「今日は何かあった」と聞いても「別にー」と生返事が返ってくるだけになるかもしれませんし、夕食に間に合わず、顔を合わさない日も増えてくることでしょう。
諸行無常です。そのことをしっかり踏まえておかねばなりません。
縁は前から。
生きておればどんなご縁に遇わせていただくのやら。
今の時を楽しまんかな。
2023年06月10日
今月の掲示板 2023年5月

実は、僕らはすでに多くのものを受け取っている。
言葉や食事、自然の恵みや先人の営為を
すでにありがたく受け取り、先祖や死者に対する
弔いの念を持っている。
まずは「受け取ることで 生きている」ことに
気付くこと。
受け取る主体になること。
人が本当に欲しているものは 何か
物には代わりがあるが、私の代わりはない。
他力の教えは 如来回向です
私たちの努力というもの一切が
間に合わない というところで
如来のハタラキに出遇うものなのです
自分が 自分になるということが
一番大事なことだけれども
案外 なれないのでは
自分が生まれてきたことが
あらゆる人に
2023年06月10日
本堂に座って 2023年5月

近ごろ各地の学校で、放課後や学校に行かない選択をしている子どもたちの「居場所づくり」という話を聞くことが増えてきました。
放課後については、保護者の帰宅時間まで学校に残る時間・場所を作ってくださっています。
また学校に行かない選択をする子には「フリースクール」が増えてきています。そんな子どもたちの「居場所」について、小沢牧子さんが書いてくださっています。
多くの専門家、とくに「有名な」専門家は、社会を動かす権力をもつ人びとの意向や都合を、学問的な言葉を使って世の中に流す仕事をしている。
だからその言説は、しばしば人びとの生活を、事実からズラしていく。
それなのに、専門家とはえらくて間違いはしない人ということになっているから、生活の事実つまりほんとうのことのほうが軽視され、ゆがめられ、ときには覆い隠されてしまうことが、あちこちに起こる。
親子関係とくに母子関係ばかりが強調され、その陰に「子子関係」の大切さが見えにくくされてしまうのも、そのひとつだ。
子どもと暮らせば、子どもが「友だちといっしょにいたいよ」と、いつも身体で伝えていることがよくわかるのに。
子どもがいちばん元気で満足した顔をしているのは、友だちと思い切り遊んだときだと、まわりのおとななら誰でも知っているのに。
学校に行っている子どもたちについても、もちろんおなじだ。
ところが学校といえば、とかく学力、進学、規則への服従と、おとなの願望ばかりが語られる。昨今の学力論争も、子どもの事情とは無関係に白熱するばかりだ。
もちろん学校制度は、国家という権力がつくったものだから、基本的には、その都合に支配されている。残念でも、それは否定しがたい現実だ。
しかし一方で、そこに集まり過ごす子どもたちの側の現実も、またある。子どもの現実認識に沿った定義は、「学校とはいろいろな友だちと過ごす場所のこと」というものであろう。
それはシンプルな事実そのものであり、しかも子どもの日常にとって、重要な意味を持っている。
子どもはみずから学び育つ生きものだが、そのためには何がしかの元気が必要で、その元気は仲間といっしょにいることで生まれるからだ。
その意味では、地域の学校ほど便利で貴重なところはない。
子どもが住む身の丈の地域、その地域に暮らすさまざまな子どもたちが、一日の長い時間そして何年にもわたる長い期間を、いさかいやもめごとをも含めて、なじみ合って過ごすことができるのだから。
子どもはおとなに、暮らしの原点を思い起こさせる。
「学校は、地域の仲間と過ごす居場所」も、譲れない原点のひとつだ。学校に通わなくなった子どもたちや親たちが求めてつくった場所は一般に「居場所」とよばれる。
学校外の「居場所」はこの十数年の月日のなかで、増えていく一方だ。「学校には行かないで、居場所に行っている」という子どもにもたびたび出会う。
「居場所」はますます数を増やしていくのだろうか。でも、ちょっと待てと思う。学校の居場所性をあきらめてはならないと思うからだ。
学校には期待できないからと、学校の外に居場所をつくることは、いま現在がだいじな子どもにとって現実的な方策なのだとはわかっている。
そこで解放された子どもたちの元気さに接すると、いつもうれしい。しかし、居場所性はどの子にとっても重要なのだ。まさに学校のなかにこそ。
もし、居場所を望む子は学校の外へ、学校にくる子は居場所性など期待するな、と二つに分けられていくとしたらそれこそ問題だ。
地域の学校に、さまざまな子どもが集まる。親たちが出会う。基礎的な学習もだいじだが、学校の居場所性もそれに劣らずだいじだと考えつづけたい。
(『子どもの場所から』小沢牧子 著 小澤昔ばなし研究所発行より引用しました)
子どもたちにとって「居場所」があることはとても大切です。小沢さんも言われますが、できることであれば、特別な場所を作るのではなく、学校や家庭・近所の遊び場など、日常的にいられる場所が「居場所」となるよう考え続けたいものです。
2023年06月10日
今日も快晴!? 2023年5月

3月に、音楽家・アーティストの坂本龍一さんが亡くなられました。
ミュージシャンとしての活躍はもちろん、環境問題や憲法をはじめとした諸問題に関する運動に積極的に参加・発信された方でした。
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から12年となったことに合わせ、坂本さんが東京新聞に寄稿された文章があります。
直腸ガンとの闘病の最中に、最後の力を振り絞って届けて下さったメッセージを是非紹介したいと思います。
「2011年の原発事故から12年、人々の記憶は薄れているかもしれないけれど、いつまでたっても原発は危険だ。いやむしろ時間が経てば経つほど危険性は増す。コンクリートの劣化、人為的ミスの可能性の増大、他国からのテロやミサイル攻撃の可能性など。なぜこの国を運営する人たちはこれほどまでに原発に固執するのだろう。ロシアによるエネルギー危機を契機にヨーロッパの国々では一時的に化石燃料に依存しながらも、持続可能エネルギーへの投資が飛躍的に伸びているというのに。わが国では、なぜ未完成で最も危険な発電方法を推進しようとするのか分からない。発電によってうまれる放射性廃棄物の処理の仕方が未解決で増えるばかり。埋める場所もない。事故の汚染水・処理水も増えるばかり。事故のリスクはこれからも続く。それなのに何かいいことがあるのだろうか。世界一の地震国で国民を危険にさらし、自分たちの首もしめるというのに、そこまで執着するのはなぜだろう。」
また、2020年5月の「朝日新聞デジタル」に掲載された「『芸術なんて役に立たない』そうですけど、それが何か?」という見出しのエッセイも、私たちの社会がどんな方向に向かうのか、考えさせられるものでした。
「でもね、根本的には人間にとって必要だからとか、役に立つから保護するという発想ではダメです。芸術なんてものは、おなかを満たしてくれるわけではない。お金を生み出すかどうかも分からない。誰かに勇気を与えるためにあるわけでもない。例えば音楽の感動なんてものは、ある意味では個々人の誤解の産物です。理解は誤解。何に感動するかなんて人によって違うし、同じ曲を別の機会に聴いたらまったく気持ちが動かないことだってある」、「僕自身、音楽を聴いて癒やされることはありますよ。でも、それは音楽自体が力を持っているということではない。僕の音楽に力なんてないですよ。何かの役に立つこともない。役に立ってたまるか、とすら思います」
かつてナチス・ドイツはワーグナーの音楽を国民総動員に利用するとともに、ゲルマン精神の涵養に役立つ芸術とそうではない芸術を峻別した。芸術に体制賛美を担わせ目的に沿う作品のみを支援したのは、戦時中の日本や旧社会主義圏の国々も同様だ。
「そういう悪い見本が近い過去にあるんです。文化芸術なんてものは、必要があって存在するわけではないと思った方がいい。だから、行政の側が支援対象を内容で選別することはもちろん、作り手側が、何かに役立とうとか、誰かに力を与えようなんて思うことも本当に不遜で、あってはならないことだと思います」、「芸術なんていうものは、何の目的もないんですよ。ただ好きだから、やりたいからやってるんです。ホモサピエンスは、そうやって何万年も芸術を愛(め)でてきたんです。それでいいじゃないですか」