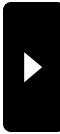2025年03月11日
今日も快晴!? 2025年3月

2025年02月04日
今日も快晴!? 2025年2月

2025年01月06日
今日も快晴!? 2025年1月

2024年12月26日
今日も快晴!? 2024年12月

2024年11月08日
今日も快晴!? 2024年11月

元々体育会系で運動が大好きな私は、境内の掃除にはまっています。守綱寺は、春夏は草取り、秋は落ち葉掃き、冬は竹やぶ整備と1年を通してやることがあります。掃除の効能として、①適度な運動が出来る。②汗をかき、新陳代謝が活発になる等、ダイエット効果抜群なのは言うまでもなく、③太陽の光を浴び土壌の微生物に触れ、免疫力がアップする。④ビフォー&アフターが分かりやすく、達成感がある。⑤顔を合わせた方に「ご苦労様です」と声を掛けて頂ける等々、良いことばかりです。
自然豊かな境内で作業していると、大げさではなく、人間は自然には勝てないなぁ。地球は本来植物のもので、人間は少し間借りさせて貰ってこの地上に住まわせて貰っているのだと感じます。
草取りに燃えていたこの夏、僧侶と臨床心理士の二足わらじの譲西賢さん(真宗大谷派大垣教区慶圓寺住職)の講演を聞く機会がありました。その中で「境内は『世間庭』」というお話がありました。
「私は今所属している組の副組長をしています。(先週末)通常組会と通常組門徒会が、私が預かっているお寺で開催されました。(略)草を除ったり庭を掃いたり戸外の掃除が大嫌いで、せんべいを食べながら寝っ転がって、韓流のテレビを観るのが大好きといううちの坊守さんは、煩悩の林・生死の園にどっぷりつかっておられますから、大変だったみたいです。だって、組内のご住職さんが全員来られるのです。お寺の代表である門徒会員さんも全員来られるのです。そういう話になってくると一生懸命、嫌でも庭を掃くのです。「このお寺は綺麗やな。坊守さんがしっかりしておられるのやなあ」と言われたいようです。もうまもなくうちの境内の門前に境内の庭の名前の札を立てようかと思うのですが、どういう名前かというと『世間庭』(笑い)」。
お話を聞いている最中に、吹き出してしまいました。これはまさに私のことだと思えたのです。以前、本堂の前で草取りをしているときに、お墓参りに来られた女性の方があったので、「こんにちは」と挨拶したら、「ちょっと!うちのお墓に行く通路の草が全然取ってなかったわよ!孫を連れてお墓参りに来たとき、靴がドロドロになって本当に大変だったのよ!」と、すごい勢いで叱られたことがありました。確かにその方のお墓は墓地の一番奥にあり、広場がすぐ脇まで来ているので草もよく生えるのです。本堂を中心に掃除を始めると、なかなかたどり着けない位置にありました。「それは申し訳ありません」と言いながら、(家でゴロゴロテレビでも見ていて叱られるなら分かるけど、私、今草取りしてたよね?毎日汗だくになって何時間も草取りしているのに、こんな風に叱られて、ああ、情けない・・・)と、何だかものすごく嫌な気持ちになったのです。多分私は、「このお寺は綺麗やな。坊守さんがしっかりしておられるのやな」」と言って貰えることを期待していたのだと思います。
「本当に世間体という煩悩があるから、掃除が出来るのです。(略)韓流のテレビを観るより、嫌でも掃除する方が自分には得だと計算できるから、掃除ができるのです。(略)私たちは、こういう世界に生きているのですよね。だから仏法に聞かないといけないのです。自分に生まれた意義と生きる喜びと出遇うには、あまりに当てにならない自分であることを気づき、阿弥陀ナビに導いてもらうために聞法するのです。清く正しく美しく完璧な自分になるために聞くのではなく、そうなれない自分に気づかせてもらうために聞くのです。」(『園林のナビゲーション』より)
本当にその通りだと思えました。清くも正しくも美しくもなく、世間庭を一生懸命整える私を、それで良いよと受け止めて下さる阿弥陀さまがあるからこそ、安心して掃除に励めるのだと思えました。
2024年10月23日
今日も快晴!? 2024年10月

2024年10月23日
今日も快晴!? 2024年9月

2024年10月23日
今日も快晴!? 2024年8月

2024年07月08日
今日も快晴!? 2024年7月

2024年07月08日
今日も快晴!? 2024年6月