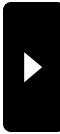2019年05月20日
お庫裡から 2019年4月

花まつりチャリティ筍コンサートも回を重ねて、今年で15回を迎えることとなりました。
平成元年の「親と子の音楽とお話の夕べ」(連続10回)に始まり、「お寺のコンサート」(11回)と続き、春に「筍コンサート」を立ち上げ重複させた後、今は「花まつり チャリティ 筍コンサート」に全力投球。
いよいよ開演も間近です。
全くの素人が作る手作りのコンサートなのに、友人・仲間・足を運んでくださるお客さま・演奏してくださる音楽家、多くの多くのみなさま方のお力をいただいているおかげです。
ありがとうございます。
「プロの方の演奏が、こんな間近で聴けるなんて」とお客様に喜んでいただき、「足元にお客さんがいて、心地いい緊張感だった」と演奏者の方に言っていただくと、本当に嬉しくなります。
また、会場が本堂であるということに主眼を置いています。
2時間のコンサートの真ん中の15分~20分、必ず「仏さまのお話」を入れます。
住職のこの時間が好きと言ってくださる方もあり、ますます張り合いをいただけます。
こうして歩ませていただいてきました。
コンサート終了後のバザーも盛り沢山。
呈茶のお菓子は、岡崎市細川の両口屋の若主人が、お店の秘伝の手法で作ってくれる銘菓まつり、限定販売します。
ゴキブリ団子に着物地のチュニック、守綱寺産ゆで筍、等々。
コンサートを助けるために始めたバザーも、余剰が出るまでになり、純益は福島原発事故・子どもの甲状腺の検査施設に届けています。
2019年05月19日
お庫裡から 2019年5月

雨マークが出たコンサート当日(4/14)。
「雨よ、降るな」というみんなの切なる願いに、雨雲は退散。会場の皆さんと、ちびっ子のいるファミリーコーラスが歌う「花祭行進曲」が開演の合図です。
堂内に用意した100脚の椅子と70枚の座ぶとんがほぼ埋まり、和やかな雰囲気の中、コンサートは進んでいきます。
メインにお迎えしたチェロの山田真吾さんは、トークもお上手でみんなをグイグイと引きつけ、アンコール曲は「G線上のアリア」と聞いた客席から「あー」と吐息とも溜息とも取れる声が上がりました。
終了後のバ
この日のみのりコーラスは、出演にバザーに大活躍。
お陰様で大盛況。
毎年好評の守綱寺産ゆで筍、寒さで上がりが悪い中、前日・前々日に8人の門徒さんが何度も何度も藪を歩き探して掘りあげ、ハソリでゆで、本当の初物をバザーに出すことができました。
呈茶も茶室と座敷の二席。
石川家の三姉弟、孫の在ちゃんが着物姿でお運び。
裏方さんもドンとおまかせできる方々ばかり。
お菓子もこの行事のために作って頂く銘菓祭。
ほのかに春の香がします。
桜といえば、4月の第2日曜日に開いているこのコンサート、14日は一番遅い巡りの日です。
裏の広場の60本の桜、年々に開花が早まり、コンサートと桜の見頃が当たったことがありません。
ところが今年は、14日も桜は満開のままでいてくれたのです。
天候にも花にも恵まれ、沢山の方々のお力で、本当に楽しい嬉しいコンサートの一日を持つことができました。
どうもありがとうございました。
こんな楽しいこと、なかなかやめられません。
体力を温存させて、また来年も頑張りたいと思っています。
来年の企画、お楽しみに。
2019年05月19日
今月の掲示板 2019年5月

あてはずれ
あてはずれ
あてはずれ
あてはずれつづけて
あてはずれてもいい
大地に立つ
宝もの
いかり はらだち
そねみ ねたみ
おおく ひまなく
もてあましとる
この煩悩が
かけがえのない
宝ものとは
退一歩
突き進むより
もう一度
問い直すことの方が
大事なように思われる
苦と楽と
地獄とは
楽を求めて苦しむ世界
極楽とは
苦を転じて楽しむ世界
そのどちらにもつけず
苦じゃ楽じゃと
迷うている私
大悲無倦
浄土への道聞きながら
地獄より
ゆき場のない身に
いま大悲の光
倦くことなし
障害
いろいろと
覚えたばっかりに
愚者になれず
身動きがとれません
三悪道
世の中が便利になって
ものがあり余り
念仏が忘れ去られて
聞こえてくる言葉は
あさましや
地獄 餓鬼 畜生の三悪道
仏はただ念仏せよと
古き時代の言葉を思いおこせよと
呼びつづけてくださる
後生の一大事
解散 総選挙
日本の方向を選択する
2019年05月19日
本堂に座って 2019年5月

先日、あるお寺さんの寺報を開いて、とても久しぶりに小沢牧子さんの文章を目にしました。
10年ほど前に講演会でお話を聞き、また『子どもの場所から』という本を何度も読み返し、子どもたちとの接し方にとても貴重な助言をいただいた、そんな中から、こちらの文章を紹介します。
雨あがりの午後のこと、あたたかな陽ざしのなかを、ひよこ色のセーターを着た一歳の息子と出かけ
息子はいま、よちよち歩きをはじめたばかりの人間初心者である。
とつぜん彼が道ばたにしゃがみこんだ。
何かに見とれている。
私もつられて彼の隣にしゃがんで、いったい何があるのかとのぞきこんだ。
道ばたにはむき出しの排水溝があって、そこを流れる水に、子どもは一心に見入っているのだった。
わずかにくだるゆるい坂道に沿ったコンクリートの細く浅い水路に、きらめく幾何学模様を描いて、澄んだ水が勢いよく流れていた。
粗い舗装のきめが作る砂利の凹凸が規則正しい水の菱形模様を生み、陽をあびて光りながらどこまでも続いていく。
それは思いもかけない美しい世界だった。
私は驚いた。毎日急いで通りすぎていたなじみの道とありふれた風
そのなかに、小さな雑草の列にかくれて、水が絶えまなく描きだすこんな光景が広がっていたとは。
たまたま小さな子どもにつられてのぞきこむことがなかったら、決して気づくことのなかった視界だ。
大人になった人間にとって、道はただ歩き過ぎるための場所なのだから。
もし大人が道ばたにひとりしゃがんで溝をのぞきこんだりしていたら、どうしたの、気分が悪いのですかと、通りかかった人にたずねられてしまうだろ
まだ人生をはじめたばかりの子どもにとっては、毎日が新しさの連続だ。
だから子どもの目はたいてい、大きく丸くひらかれている。
大人は子どもを抱き上げ遠くを見せ、鏡をのぞかせ笑わせなどしては、子どもが生まれてきたこの世の中を見せる。
しかし大人が子どもにするのとおなじように、子どももまた大人の世界を揺るがせ、広げ、おどろかせ、楽しませるのだ。
文字どおり、おたがいさまに。
子どもと暮らすことは、人生を二度生きることだなあ、といつも思っていた。
自分もこんなふうにしておとなになったのか、人間誰もがこんなふうにして育っていくのか、と。
おとなになって当たり前になっていることでも、子どもにはすべてが新鮮だ。
虫を見つけても木の葉が落ちても雪が降っても、どれもはじめて出会うことばかりなのだから。
道ばたの石ころさえも。おとなの生活になぞらえれば、いわば毎日、新しい国を旅行しているようなものだ。
日常に飽きることなど、あるはずがない。
おとなは、自分にとっては見慣れた日常を、子どもに連れられてもういちど旅するのだ。
「そうか、なるほどね」と、あらたに発見し、おもしろがりながら。
ときどき、若い母親たちのための講座に招かれる。
「毎日おなじ生活で、子どもが飽きるだろうから、どこかへ連れていってやりたい」という若い親がいた。
わたしは、「小さな子どもはなんでも珍しいのだから、子どものためにわざわざ連れ出さなくてもいいのじゃない?親をやるのは疲れることだから、あなたが行きたいところへ連れていって、自分のやりたいことにつきあわせるなら別だけれど」と言った。
「ああそうか、子どもはおとなのすることをなんでもやりたがりますものね、生活に飽きるなんておとなの考えなんですね」と、その人は答えてくれた。
「おなじ絵本ばかり読んでほしがるんです。
いろいろな本を読んであげたいと思うのだけれど」と言う人もいた。
「自分のお気に入りができたのね、その絵本をいっしょに楽しんであげたら子どもはきっとうれしいでしょ」と、わたしは言った。
なんだか先輩づらばかりしているな、と苦笑しながらも。
でも、一方的に意見を言うばかりではない。
世代のちがうわたしは、考え迷いながら現代を生きている若い親たちから、いつもたくさんのことを学ぶ。
小さな子どもと、若い親、その親世代、みんな順繰りおたがいさまに、子どもを仲立ちにして教わりあい、子どもをきっかけに、考えあっていく。
暮らしの問題、社会のしくみ、時代と世界のありよう。
おとなは子どもを介して、日々いやおうなしに考え、いつのまにか自分たちの視野をひろげ、考えを深めていく。
子どもはいつの世も、おとなの無心な案内人だ。
(『子どもの場所から』小沢牧子 著 小澤昔ばなし研究所発行 より引用しました。)
近所の新1年生の男の子は、下校の際にふと立ち止まっては虫や花を見ているそうです。
通学班長の在ちゃんは、並んで歩かせるのに一苦労の様ですが、この文章を読んで、こんな子どもらしさを大事にしてあげたいなぁ、と感じました。
2019年05月19日
清風 2019年4月

にんじん(人参)よりは、
だいこん(大根)がいい
人身(にんじん)受け難し、今すでに受く
(「三帰依文」冒頭の言葉)を聴いた、幼児の発言
お勤めの前には「三帰依文」を読むのですが、寺では家族が揃いやすい夕食の前に夕時勤行をすることにしています。
孫の在ちゃんが、まだ保育園入園前後の頃だったと思います。
「三帰依文」の最初の言葉「人身受け難し、いますでに受く」の「人身」を「にんじん」と詠み慣わしていますので、いつものように「にんじんうけがたし…」と読み、終わったところで在ちゃんが「おじいちゃん、にんじんは苦いし臭いも好きじゃないから、私は大根がいい」と言いました。
仏教の言葉は、中国の呉の時代の読み方をすることがあります。今の日本では
ふつう「人身」は「じんしん」と読みますが、三帰依文の読み上げは、仏教の伝
統的な読み方 ― 呉音読みで「にんじんうけがたし…」と詠み慣わしています。
その時は、その在ちゃんからの「異議申し立て」に可愛いな…と思ったぐらいに聞き流していたのですが(在ちゃんもこの4月から6年生です)、先日あるところでの法話にうかがって、この「にんじんよりは、大根がいい」という発言を紹介しながら、初めて何気なく「大根」と板書しました。
話としてはこれまでにも紹介していましたが板書したのは初めてで、「大根」と書いてみてあらためて気付いたことがありました。
それは、大根の「根」の字についてです。
『大辞典』には、「根本原理、根本となり動かすべからざる原理」
『広辞苑』には、「根、よりどころ。物事のもと」
などの意が出ていました。
「大根(だいこん)」は、「大きい」というか「深い」というか、そういうメッセージの込められた言葉であるということです。
「根」そのものが、そういう意味を持つのでしょうが、それにたまたま「大」の字が付いて「大根」と。
考えてみると、どうでしょうか。
私ども、人間の生きているという営みは、要するに一言で言えば、言葉そのものの表現している「大根(根本となるよりどころ)」を求めて…ということになるのではないでしょうか。
いわゆる、人間の営みの集積である歴史というものは、洋の東西を問わず、大根(根本となるよりどころ)を求めてきた歩み(=歴史)と言えるのではないかと思うのです。
人間の歩み(歴史)とは、本当に安らげる ― 不安・不平・不満の無い、過去には感謝・現在には満足・未来には希望を持てる ― 社会・国を求めてきたのです。過去の先人達も、結果(というか評価)は様々に分かれるでしょうが、その時代にあっては「自分の国を愛するのに、どうして他人の国を憎まねばならぬ必要があろうか」〔中野重治 作家〕との発言もあるのですが、結局は治安維持法などで、そういう発言は認められず、愛国という(正義の?)旗印を立てて“鬼畜米英”という結果になって、殺し合いをしてしまいました。
「私には、敵は いない」(劉暁波(リュウ・シャオ・ポー) 1949年~2017年 2010年ノーベル平和賞受賞)この言葉はリュウ氏の遺言として一考しなければならないのでしょう。
次に安田理深(1900年~1982年 思想家)は、師・曽我量深のその生涯にわたる念仏についての思索を、「念仏の仏教を、単なる救済でなく、自覚自証の途としてみなおしてくるところに革命的な意義がある。」と言い、「よく考えれば、宗教を救済としてのみ見るのは、人間の自己肯定である。」、それなら「根元的意味でのエゴイズムである。それを破って、人間をして深い根元に呼びかえす、自覚こそ宗教の本質でなくてはならぬ。」(『清風』2018年11月号1面の言葉参照)と述べています。
さてあなたは、生きる上で何を「大根(根本のよりどころ)」として生きていますか?
これらの先人のご苦労を手引きとして、上に掲げた問題意識(「大根」)を考えていきたいと思います。
4月14日(日)午後1時開演、花まつり チャリティ 筍コンサート。
皆さま、どうぞお出かけください。
2019年05月19日
今月の掲示板 2019年4月

自分について
うぬぼれたり のぼせたり 悲観したり
どれも 自分を失っている
自分の心に 相手になって
自分の心に 縛られている
我々は 計らいを越えた世界を
計らいでつかんでいる
だから、狭いし暗いし
安心できないし、満足もない
ものを もの以上に 考えない
もの以下にも 考えない
金さえあれば 何でもできる と思う
大事なものほど 金では買えない
金は 金以上でも 以下でもない
金の奴隷には ならない
人間は
自分の考えておることが正しい
己が正しい とし
他人を間違いとする
人間の悪い病です
人生というものは、
行き詰まったりするもので ない
ちゃんと成るようになっている
それを 不思議という
2019年05月19日
今日も快晴!? 2019年4月

その電話は、3月初めの21時過ぎに突然掛かってきました。
暗い低い声の、呪いの電話です。
「おねえちゃ~~ん。明後日、帰ってもいい?戸谷くん(ご主人)が、2月仕事が忙しくて2日しか休みが無くって、しかもその2日も半日しか休めないんだよ~。ののちゃんとさちくん連れて帰っても良いかなぁ?」と、東京で流行のワンオペ育児に勤しむ妹からでした。
「いいよ!いいよ!帰っておいでよ~!」と即答し、2日後、到着時間に合わせて駅まで迎えに行くと、
「よ、夜逃げか!?」と思うような出で立ちで妹が駅から出てきました。
背中には巨大なリュックを背負い、4ヶ月のさちくんを抱っこひもで支え、2歳のののちゃんをベビーカーに乗せて、持ちきれないほどの荷物がベビーカーの取っ手にぶら下がっています。
「えらかったね~!よく一人で帰ってきたねぇ。」と迎え、妹の話を聞いてゆくと、よくそれでやっていたね・・・というような、なかなか大変な状況でした。
「東京じゃ、ママ友達一人もいないんだよね。」
「お義父さんもお義母さんもまだ仕事しているから頼れないし・・・。」
「マンションでね、別の部屋の人から苦情が来るんだよ。子どもの遊ぶ音がうるさいって。そんなに遅い時間でも無いのに・・・。」
「エレベーターで知らない男の人から『子どもは3人は生まないといけない』と言われたけど、それなら旦那さんを家に帰して欲しいよね~。」
「戸谷くんが休みがないってことは、私にも休みがないってことなんだからさぁ」等々・・・。
ああ、本当に大変だなぁ。
田舎の実家暮らしで母や家族に囲まれ、妹のような子育ての苦労など何一つしてこなかった私なので、本当に妹は立派だなぁ、よく一人頑張っているなぁと頭が下がります。
妹の帰省中に、豊田で起こった悲しい事件が新聞に掲載されていました。1
1ヶ月の3つ子の子育てでノイローゼになった母親が、成長の遅かった真ん中の子どもを畳にたたきつけて殺害した事件の判決が出たという記事です。
「不妊治療の末、やっと授かった子どもだった」
「飲食店を経営している自分の両親も、夫も頼れなかった」
「1日24回のミルクで寝られず、子どもの泣き声に苛立った」
「市の相談窓口に行ったけれど、双子の子育てのパンフレットを渡されただけだった」
「子どもが可愛くないわけでは無かったが、3人同時に泣かれたらどうしたらよいか分からなかった」等々・・・記事を読みながら、涙がこぼれました。
「なんてひどい母親だ!」とは、到底思えませんでした。
口を突いて出たのは、「分かる!」という言葉だったのです。
子どもたちがまだ幼かった頃、子どもが寝ない!と苛立ったことや、予定通りにいかなくて腹を立てたこと、殴りつけたいと思ったことは数え切れないほどあります。
同じ状況に置かれたら、私も子どもを床にたたきつけていたかもしれません。
そんなことを考えていると、ふと「さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべし」という歎異抄の親鸞聖人の言葉が浮かんできました。
自分はたまたま環境に恵まれていたお陰で、残虐な振る舞いをせずに済んだだけなのかもしれない。
条件さえ整えば、いつ自分も同じことをしでかすか分からない。
人間とは怖い存在で、普段は「良い人。良い姉。良い母」を演じようとしている自分の化けの皮もいつ剥がれるのか・・・。
そういえば、妹は二週間でそそくさと東京に帰って行きました。
すでに「良い姉」の化けの皮は剥がれていたのかもしれません。
・・・ぺろ~り・・・。
2019年05月19日
清風 2019年3月

「清風紙」1月号・2月号の一面で紹介した浅田正作さんの詩の題と語句を改めて紹介します。
1月号は「ここ」と題し、「ここに居て喜べず ずい分 よそを捜したが ここをはなれて 喜びは どこにもなかった」。2月号は「足もと」と題し、「なにもかも 当たり前にしているほどの不幸が またとあろうか 如来(ほとけ)はつねに 足もとの幸せに気づけよと 仰せくださる」
これは、冒頭で紹介した釈尊の言葉に呼応している人の受け取りと言えるのではないでしょうか。
この詩で紹介した内容が、実は、現実の私の暮らしで飽きずにしていることで、「人が本当に何を欲しているのかを知るのは、多くの人が考えるほどに容易なことではないこと、それは人間が誰でも解決しなければならない最も困難な問題の一つである」と(「清風」先月号2面に)指摘していることなのでした。
「よく考えれば、宗教を救済としてのみ見るのは、人間の自己肯定である。根源的意味でのエゴイズムである」(2018年11月号1面)という安田理深先生の言葉を紹介させてもらっていますが、要するに親鸞という人は、私たちの宗教観を改めて問うてくださった方ではないかと思います。
宗教観とは宗教をどのように見ているか、受け止めているのか、ということなのですが、少し角度を替えてみれば、幸せについてどのように考えているのかと、一度立ち止まって考えてみるということで
身近なことで言えば、丁度今は受験シーズンの3月ですから受験生の親さんから言えば、何と言っても志望校に合格することでしょう。天神さまへ行ってお札を求め、志望校への合格を祈る方も居られることと思います。子のため、また孫のためと。
合格すれば、当座はそれで良かったというわけですが、しかし入学してみれば、当然のことながら校内ではみんな合格した生徒・学生ばかりです。つまり入学してみれば、合格した喜びは受験生本人からすればもう過去のことで、当たり前の日常生活にもどります。校内での成績が、また当然のことながら、関心事の中心となります。また、志望校を受験し、その希望が適わなかった場合は、第2の志望校への進学ということにしなければならないでしょう。
しかし、その合格・不合格いずれにしても、そのとき、受験できた健康な身体と能力を与えられていたことは、もうこれも当たり前のことになります。
宗教観の一つの典型例として受験を例にしてみたのですが、ここで遠藤周作さん(作家、カソリック教徒)の宗教観を紹介することにします。
「神も仏もあるものかというところから、本当の宗教は始まる」
「私の都合」が作り出している神・仏、それはエゴ(基準は自分の都合に合うか、合わないか。
合えばいただこう、合わなければ排除する)が対象的に作り出しているのであって、狐や狸まで神として祀られていることもあります。
因みに遠藤さんは、自分を「狐狸庵」と称しておられました。
私はこの遠藤さんの狐狸庵という名告りに、私たちが平常忘れ去ってしまっている奥ゆかしさ、本当の意味での謙譲、懐の深い人間観を教えられる心地がします。
これは、大岡昇平さんの作品『俘虜記』の本文、冒頭に添えられてある「わがこころのよくてころさぬにはあらず」(我が心の善くて殺さぬにはあらず)(『歎異抄』第13章)の言葉とも、響きあっていることを感じます。
これらの作家の作品の心情の底を流れているものこそ、上に掲げた安田先生の文章には、続いて「それを破って人間をして深い根元に呼びかえす、自覚こそ宗教の本質でなくてはならぬ」(2018年11月号「清風」冒頭の文)と記されている、「人間を深い根元に呼びかえす」と言われている、その根元に気づいた人の生き様なのでしょう。
その「深い根元」とは、誕生の言葉それ自身、「私は生まれた」という表現に示されていたのです。
その「深い根元」からの呼びかけ、浅田正作さんの詩で言えば題の「ここ」「足もと」なのですし、それこそが冒頭の「あなたは あなたで在ればよい。あなたは あなたに成ればよい。」という言葉であったのでしょう。
2019年05月19日
清風 2019年5月

人間とは
その知恵ゆえに
まことに深い闇を生きている
高史明(コ・サミョン) 作家
1932年下関生まれ、在日朝鮮人2世。高等小学校中退。
親鸞聖人の教えに縁を結ばれる。
著書『念仏往生の大地に生きる』『真実のいのちに導かれて』
(いずれも東本願寺出版部発行)他多数
私ども人間は他の生き物とは異なり、意識・理性を備えています。
その知恵のおかげで、いわゆる進歩・進化を遂げてきました。
しかし、その進歩・進化は、逆に退化と呼ばれるような様相を帯びつつあることが、知られるようになってきました。
例えば地球温暖化と言われるように、人間のエネルギー消費が、他の生き物が持続して生息するのに困難とされる地球環境の破壊をもたらし、その原因とされるCO2の排出量を減らすという施策を行い、特にGNP(国民総生産)の高い国に対しては達成目標数値を示す事態となっています。
先月号では「人身受け難し」という三帰依文の冒頭に置かれている言葉を紹介しながら、人身(野菜の人参、そして大根)という幼児の言語感覚に教えられて、私たちは何を生きる上での大根(根本のよりどころ)として生きようとしているかを考えてみました。
仏教の基本的な教えを語る言葉としての「縁起(因縁生起)」、それをもう少し説明している「重々無尽 法界縁起」という言葉をご存知でしょうか。
「重々無尽」とは互いに関係し合って際限の無いこと、また「法界縁起」とはあらゆるものが互いに縁となって現れ起こっている、という意味とされています。
こんなことを語られている本に出会いました。
普通、日常的な時間と神話的な時間があって、その片方の日常的時間だけを思っているときもある。
「早く早く、ご飯を食べないと遅れるわよ」と言ったときに、その時のお母さんの考えは日常的な時間で、これは神話的時間ではない。
それにせかされている子どもも神話的な時間ではない時間を生きていることになります。
東京で調査したところが、子どもがお母さんから聞くことばの中で多いことばは、「はやく、はやく」だそうですよ。
「はやく、はやく」って、これは神話的時間じゃないんで
これは近代的時間です。能率的なその瞬間の中で生涯を過ごすとどうなんですか。
五十年、六十年生きていても、早く早くで生涯終わってしまったらどうなんでしょうね。
文学にも何にも縁がないですよ。
『神話的時間』熊本子どもの本研究会刊 1998年1月9刷
鶴見俊輔(1922~2015年)
ハーバード大学で哲学するということ、「生きるとは思索する、考えるということ」であることと学ぶ。
1946年、雑誌『思想の科学』創刊の中核を担う。
ベ平連などの社会運動にも参加。
そこで「根本的なよりどころ」を考えるヒントとして、冒頭の高史明さんの言葉と、上記の鶴見さんの『神話的時間』の一節を紹介しました。
これらの言葉を紹介するのは、「清風」昨年11月号1面で紹介した安田理深先生の言葉、「念仏の仏教を、単なる救済ではなく、自覚自証の途としてみなおしてくるところに、曽我先生の思索、学びの)革命的な意味がある。
(略)人間をして深い根元に呼びかえす、自覚こそ宗教の本質でなくてはならぬ。しかもその自覚は理知的というよりも、根元の深みへ呼びかえし目覚ますという意味での自覚である。」に、実は導かれてのことなのです。
冒頭の高史明さんの「人間とは、その知恵ゆえに、まことに深い闇を生きている」という指摘は、私たち人間にとっての“大根”とは、自己の他に求められることではなく、私の知恵・理性の底(根っこ、内観するその気づき)にこそあるのだと見出したのが仏教(佛陀の教え、目覚め・気づきの教え)であったからです。
仏教の「救い」とは、これから努力して実現する次元のことではなく、すでに救いのド真ん中にいるのにそれに気づけない私である、という目覚めから出発することであったのです。親鸞聖人の言われる「難信」も、そういう意味であるのです。
私の知恵・分別こそが、私を救いから遠ざけていたのです。だから「ただ念仏」の教えは「難信」と言われてきたのです。
「苦悩する」というのは、既に与えられているからこそ、生じるのです。
2019年05月19日
本堂に座って 2019年4月

しばらく前に購入していながらなかなか読めていない、という本(積ん読というそうで…)が何冊もありますが、ようやく開くことができた本『生きる職場』について紹介したいと思います。
この「職場」・パプアニューギニア海産では、「好きな日に働き、好きな日に休む。好きなことを優先させ、嫌いなことはやらない。」という働き方が採り入れられています。
その働き方の内容や発想の原点は、次のようなものです。
はじめに取り入れたのが「フリースケジュール」という制度です。
毎週決められた曜日に出勤するという、これまでの会社の常識を変えるところから始めたのです。
要するに「好きな日に出勤すればよい。連絡の必要はありません」というだけのことなのです。
うちの工場で働いているパート従業員は子育て中のお母さんたちです。
そんなお母さんたちが働きやすい職場をと考えたときに、僕が真っ先に思いついたのが「好きな日に休める会社」でした。
小さな子どもがいつ熱を出すかいつ怪我をするか、運動会や授業参観といった学教行事だって頻繁にあります。
そんな時、会社に気兼ねせず心置きなく休むことができたらどれ程いいだろうと考えたのです。
もう一つ、僕たちの工場では、「嫌いな作業はやらなくてよい」というルールを作っています。
人はそれぞれに好き嫌いがあり、得手不得手があります。
それは仕事でも同じはずです。
当然、嫌いな作業を担当することになれば、嫌な気持ちで仕事をすることになりますし、自分が好きな作業をほかの人ばかりがやっていれば、その人に対しての不満が募ります。
ですから、こういった個々の向き不向き、好き嫌いの多様性を仕事の中に取り入れられたら、さらに働きやすい職場が実現できると考えたのです。
それが「嫌いな作業はやらなくてよい」というルールです。
僕は従業員に「早くして」とは言いません。しかし「一生懸命やってください」とか「集中してください」と言うことはあります。
似たようなニュアンスに感じるかもしれませんが、これは全く違う言葉です。
人には得手不得手がありますから、一生懸命やって遅いのは問題だと思いません。
じゃあ遅い人がいたらどうすればいいのかというと、その人を急かすのではなく、その遅い人が少しでも早く仕事ができる、またその人が力を発揮できるような職場環境を整えるということが必要です。
このルール作りからも分かるとおり、働きやすい職場を作っていくには、これまでの常識からの発想の転換というものがとても重要になります。以前は、午前中だけ働いて帰ることを「自分の都合を優先させて楽をしている」と考えていましたが、今は「午後に用事があるのに午前は来てくれた」と考え方が変わったのです。こうした発想の転換を起こすためには、まずやってみることです。実際にやってみると、それぞれの立場においての感情が出てきます。ある意味では、それが発想の転換に繋がるかどうかの答えなんだと思います。考えすぎずに、これはいいかなと思ったことは、まずやってみて、その結果が出たときの自分の気持ちが、ポジティブなのか、ネガティブなのかを見極める。ポジティブに感じたことを素直に受け止めて、これまでの習慣にとらわれず、変えるべきものは変えているにすぎないのです。
働き方を考えることと、子育ては似ています。
縛らず、強制せず、自分の力を出せるようにサポートし、仲間や友達と仲よく協力する、そのためにちょっとした秩序を作る。
そんな感じでしょうか。結局、子どもの世界や学校で問題になっていることは、大人の世界が鏡のように映し出されているだけなのではないかと僕は思っています。
過去にはうちの職場でもいじめがありました。
しかし、会社が働きやすい職場を目指して努力することによって、なくすことができました。
もし多くの会社でいじめや差別をなくすことができれば、その心地よさを実感した大人は子どもにも、心地よい社会や学校になるような知恵を与えていけるのではないでしょうか。
子どもの世界が大人の世界の映し鏡だとするならば、今の大人たちはそのような知恵や心地よさを持ち合わせていないのかもしれません。子どもは大人の背中を見ているのです。
(『生きる職場』武藤北斗 著 イースト・プレス発行 より引用しました。)
これらの働き方は「人を縛り、管理し、競い合わせる、今の会社や社会のあり方が、果たして正しいのかという疑問」が出発点で、結果として、効率・生産性・品質向上につながったのだそうです。
“管理”することが当たり前だと思っている、その当たり前を疑うところから、働き方も子育ても見直していけるのだと思います。