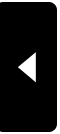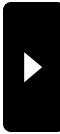2025年01月06日
清風 2025年1月

本年も、どうぞよろしくお願いします。
2025年 元旦
しかれば名(みな)を称するに、能(よ)く衆生の一切の無明を破し、
能く衆生の一切の志願を満てたまう。
『教行信証』行巻(真宗聖典P161)
無明 … 問われていることに気づけない
志願 … 根源的願い
自己とは何ぞや。
自己とは他なし。絶対無限の妙用に乗託して、任運に法爾にこの現前の境遇に
落在せるもの、即ちこれなり。
仏教には、「他化自在天」とか「魔」という物語の世界が語られています。
古代インド人は多くの天を考えてきましたが、それらの天の中で、人間がふつうに考えて一番いいなぁと思われる天が「他化自在天」と言われます。他の者が作成したものでできている天のことです。他の者が作ったものを奪って我がものとしている世界、つまり手を汚さずして苦悩を感じることなしに主人公の如く振る舞っている世界のことです。
これが言葉の定義ですが、これを現代に適用すると、以下のようになります。
今の私どもの生活の方向は、他化自在天に向かっていると言ってもいいかと思います。
我々の生活は今や、電気にしろ車にしろ、生活の全部は他化自在天という世界を目指しています。
他が作り、苦労してきたものを、みんなお金で買い取る。
もっと言えば、お金で奪い取るように我がものにして、そこの主人公となっていく=我が世界にしていく…。
このように、現在の生活は成り立っています。資本主義社会というのは、本質的に他化自在天という質を持っているのでしょう。
では懈慢界はどうでしょうか。
この懈慢界という世界も実に結構な場所であり、もちろん衣食住文句なし、そして住居は七宝でできており、寝るところも着るものも、食べるものも実に豊かで、見栄えがよくて、気持ちのいいところとして語られています。
それだけではなく、娯楽施設まで付いており、歌があり、音楽があり、踊りがあります。
例えれば、ブランド品で着飾り、一流レストランでディナーショーを楽しむようなものです。
これはまさに、現代で言えば資本主義社会にあたります。
他化自在天や懈慢界は、現代社会に対する批判的概念であると言えるでしょう。
空虚・空しさと多忙、根源的問い。「何故、生きるのか」という問い、生きられなくなっている … 現在にも未来をも、生きる術が分からない。
以上、今月号では『近代に対する仏教的批判 平野修師の仕事とその意義』(今村仁司 著)を参照しました。
2025年01月06日
お庫裡から 2025年1月

みのりコーラスでは、抒情歌でつづる睦月、如月、弥生のメドレー曲の練習を始めました。
最初の曲は『一月一日』、「とーしのはーじめのためしーとてー」で始まります。
この曲は、豊田コンサートホールのニューイヤーコンサートの時、外国から来る楽団がお決まりのように、オープニングかアンコールで演奏してくれます。
この歌を練習中に、ふっと私が「小学校の時、一月一日は学校へ行って、この歌歌ったよね」と言うと、周りは「知らない」と冷たい反応。
尚も「ほら、講堂に全学年が整列して「おめでとうございます」と校長先生とご挨拶して、紅白のお饅頭もらって帰って」の言葉も終わらない先に、「エー、お饅頭なんて学校からもらった事がない」「大体、一月一日に学校へ行ったことない」「この歌も知らない」「そんなこと、三重県だけでやってたんじゃない?愛知県じゃなかった」と散々の反応。
一応、私は戦後生まれだし、コーラスのメンバーとそんなに年の差はないと思っていたのに…。
私の独りよがりだったのか。
この歌も一番の歌詞は知っていたけれど、二番は知らなかったので、学校で歌ったのがこの曲だったのかもあやしく、記憶がだんだん朧になってきます。
そんな身が、また新しい年を迎えました。
私と成っている他力本願が、そこを生きてくれよと私に添うて、呼びかけてくださっています。
だから安心して日々を重ねられます。
明けましておめでとうございます。
今年も、どうぞよろしくお願いいたします。
尚子
2025年01月06日
今月の掲示板 2025年1月

逃げ場なし 浅田正作
いくつになっても
びっくりすることが一杯
それは
逃げ場なしの身が
思い知らされるとき
当たり前が
当たり前が 拝める
当たり前が
当たり前でなかったと
当たり前が拝めるとき
どうにも始末のつかん
わが身から
ひまもらえる
内面の声
臆面もなく
町を歩き
人と語り
なに食わぬ顔しているが
お前、自分の後ろ姿を
見たことがあるのか
鏡
毎朝 毎朝
洗面所の鏡に向かって
私は自分の何を
見ていたのだろうか
聞く身
願いを 聞こう
願われて 願われて
願われて 生きてきた
願われて 育てられてきた
その願いを
聞く身になろう
道づれ
私と妻は
三悪道という名の
道連れ
幸せという
世間の言葉に迷わずに
三悪道に
掌を合わせていこう
自力
もう 弱音をはくまいと
思っていたが
駄目だった
駄目だったので
自力とわかった
いただく
これでよかったと
言える世界は
いただく世界をおいて
どこにもないようだ
2025年01月06日
本堂に座って 2025年1月

今月は先月に引き続き、子どもの養育環境の改善に取り組まれている武田信子さんのインタビューを紹介します。
――幼児期につくられる土台が大切だということですね。
赤ちゃんは一人では生きていけない状態で生まれてきますよね。そして、いろいろな欲求が生まれた時に、その欲求に応えてくれる大人が必要です。自分の欲求に的確に応えてくれる存在が近くにいること。これが相手を信頼することにつながります。自分を助けてくれる技術や手立て、知識を持っている人にそばにいてほしいわけです。その自分の要求や生きていく為に必要なものをきちんと与えてくれる人に対して、基本的信頼感が生まれます。
何かびっくりすることが起こった時に、自分をぎゅっとしてくれるような、この人といれば安全と思えるような関係性ができていれば、次に何かあった時にその人に頼ろうとしますよね。だいたい生後7、8ヶ月ぐらいになってくると頼る人が決まってきます。そうすると、その人だけにくっついて人見知りするようになります。
ただ、最近は親が子どもの育て方、赤ちゃんの扱い方をあまりに知らないので、愛情はあっても、赤ちゃんをうまく扱えないのです。例えば大学生に、家の前に生まれたばかりの赤ちゃんが捨てられていたらどうするかと聞くと、コンビニで牛乳を買ってきて飲ますと言うんです。そんなことをしたら赤ちゃんは具合が悪くなってしまいます。赤ちゃんに対して愛情がないわけではなく、人間の赤ちゃんに牛の乳をそのまま飲ませてはいけないということを知らないだけなのです。このように、子どもが生まれた時に、何も知らずに子どもを育てようとすると赤ちゃんの立場からは虐待になり得ます。子育てを知らない人が多いのは、少子化で妹や弟、近所の子どもの世話をしたことがない人が増えてしまっているからではないでしょうか。教育虐待も親はよかれと思ってやっているわけで、子育て全体が同じような状態にあるわけです。昔は、小さい頃から身近な人が子育てをしているのを見ていたり、あるいは野菜や植物を育てたりしていましたよね。その中で、「育つ」というのがどういうことか自然に学んでいたのだと思います。
――家庭における学びや教育の観点から文化や伝統の継承をどのように考えておられますか。
赤ちゃんは生まれてすぐの頃から、自分が生きていくために、社会はどのように動いてくれるかを模索しています。どんな声で呼べば親が来てくれるかとか、手足をバタバタさせて重力を感じるとか、さまざまな試行錯誤をし、それが遊びや学びと言われるものにつながっていきます。赤ちゃんの頃は、生きることと、遊ぶことと、学ぶことと、生活することがほぼイコールなのです。そういった区別のつかないものの中から次第に言葉を学習したり、社会のルールを学習したりしていきます。そして、この基礎の積み上げが、学校という学びの場にもつながっていくのです。
例えば、「あめ」って書いてあった時に、食べる飴だとわかる子は飴を食べたことのある子です。しかも「あめ」には雨と飴という2つの意味があるということも、普段の生活の中で聞いていたからわかることです。それは学びでもあり、遊びでもあり、そういうものなんです。
だから、文化などの継承も、日々の生活の中でまわりの大人の役割や言葉遣いといったものが、いつの間にか、子どもに取り入れられているものだと思うのです。
――日本の教育について、社会を形成している私たち一人ひとりは、どのように考えていけばいいのでしょうか。
生涯学習という言葉がありますが、生まれてから死ぬまで脳の発達が止まることはないわけですから、大人だって学びます。私は子どもたちに何か特別に教える必要はそんなにないと思っています。大人たちが楽しく学んで生きている姿を見せていれば、自然と子どもたちもそれをやりたくなるのではないでしょうか。
何か教えるというよりも、日々の生活の中で自ずと感じることこそが大切だと思っています。教育って、人の姿から学ぶことだと思うので、大人たちが楽しく学んでいる姿を見せ、失敗してもそれをお互いに許し合い、支え合うような環境であることが大事なのではないかと思います。
(『同朋新聞』2024年11月号 東本願寺出版発行
人間といういのちの相(すがた)「社会の中で「子ども」は育つ」より引用しました)
2025年01月06日
今日も快晴!? 2025年1月

秋に、「豊田市 中学生と地域の大人による対話プログラム実証事業~tsumugu~」に参加しました。
友人から「陽子ちゃん、こんなのあるけどどう?」と紹介されて、(彼女が勧めるなら、きっと面白いに違いない♪)と、よく知らないまま引き受けることにしましたが、予想通り大正解でした。
tsumuguは、事前の研修でプログラムの概要説明を受けて、市内にある4つの中学校の中で、開催日時の予定の合うところを選んで訪問し、中学生の子どもたちと対話をします。
研修に参加すると、「人生グラフ」というワークシートを渡されて、横軸に自分の人生を年代を区切って記入し、起こった出来事と自分の感情を縦軸に記入してゆきます。
このワークシートを記入することがなかなか難しく、50年分の自分の人生を振り返るとなると、かなり時間が掛かりましたが面白かったです。
当日は、そのシートを持って中学校を訪問し、生徒三人対大人一人で組になります。
①自己紹介(10分)
②大人が生徒に人生グラフを紹介(10分)。
③子どもの人生グラフを見ながら順番に1対1の対話(15分)。待っている子どもたちは、代表の大人の人生紙芝居を聞く。
④まとめ:これからの人生を考える(10分)という流れで、110分の授業時間は終わります。
豊田市としては、人口減少、少子化、人生100年時代の到来等を受けて、「全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことの出来る地域社会」を作ろうとする狙いがあるそうです。
代表の深見先生の話では、子どもたちは、先生でもない、親でもない大人と対話することを通して、「本気で向き合ってくれる大人の存在がいる。自分は一人じゃない」と感じるのだそうです。
こうしたプログラムを実施しようとする人が豊田にいること、手を上げてくれる中学校があることが、まずとても良いなと思いました。
さらに当日は、体育館に集まった大勢の大人を見るだけでちょっと感動してしまいました。
私のように時間の融通が利く主婦ばかりではないのに、平日の午後、子どもたちのために仕事を休んだり、スケジュールを調整して参加しようと思う大人がこんなにたくさんいるんだと思うと、(豊田も捨てたもんじゃないな)と胸が熱くなりました。
実際に子どもたちと対話を行ってみると、どの子も自分の好きなものを見つけて、部活や習い事を頑張っていたり、学校生活を楽しんでいる様子が分かりました。
しかし、勉強面や人間関係、自分の総合評価に「微妙」と答える子が多く、「自信のなさ」を感じました。
子どもたちの話を聞いたあと、「部活を頑張っているんだね。それって凄く素敵なことだよ。」「人間関係で悩んでも、自分なりに乗り越えたんだね。頑張ったね。」「クラスのお友達と仲良く過ごせているんだね。いいね。」と、目の前の子どものやっていること、感じていることをそのまま肯定し、良いところを見つけて褒めるよう心掛けました。
大人目線のアドバイスや価値観の押しつけを行うのではなく、対等の人間として向き合うことで、子どもたちの表情がどんどん明るくなりました。自分の子育てを振り返ると、どうしても出来ていないことや足りないことに目が行き、「もっとこうしたら?」「ここがまだだね」と、先のことばかり心配して、目の前に居る子どものそのままを「良いね」と褒めることがあまりなかった様な気がします。
本当は、「今」の「そのまま」の子どもを、丸々肯定して受け止めるだけで良かったのだと、今更ながら気づかされました。
関わり方に正解がないからこそ、毎回全力で目の前の子どもと向き合うことで、大人も発見と実りの多いプログラムでした。
2024年12月26日
清風 2024年12月

人間が 人間だけでやっていく
現代の問題は そこにある(その2)
真宗法語カレンダー 2024年10月より
(真宗教団連合発行)
「人間が人間だけでやっていく」とは、どういうことを言おうとされているのでしょうか。そのことを明らかにするため、次の文章を紹介します。
どういうことかというと「平和を求めつつ核兵器を作り、長生きを願って老いた身をかこつ。よく生きたいその心を持っていると同時に、老人の孤独と身体の不自由を嘆く。豊かな社会を求めて、公害を招き寄せているというようなことです。善いことだけを願って悪いことを排除しようとするその心が、善いことを願う心で悪いことを生み出してしまうのです。それはもはや、神のせいにも自然のせいにもすることができない。人間自身が人間を否定するものを自分自身の中から生み出してしまうという、そういうことが誰の目にも明らかになってきた。
『児玉暁洋選集 10』「歎異抄に聞くⅢ」P318
現代は科学(人間の知性が生み出したもの)の成果によって進歩・進化が進み、私ども人間は生物の中で「万物の霊長」であると自称している時代となっています。「人新世」と言われ、国連の事務総長が“地球沸騰”と危機感を表現していると聞かれるように、私たちの暮らす時代を「地球史のストーリーにどのように位置づけるか」ということが話題となっています。
かつて金子大榮先生は、「人間は二度誕生しなければならない。」とおっしゃっていました。一度目は母親からの誕生です。母親には陣痛ということがあって、私が肉体を与えられました。しかし、もう一度誕生が必要であると言われます。そして一度目の誕生の時と同じ様に、陣痛が伴います。それが苦悩であるというわけです。人間はただ悩むのではなく、悩むには悩む意味があるのです。これは、自己ならざるものを自己としているから悩むのであり、苦悩とは自己が誕生しようとしている兆しなのです。
人間は誰しも、幸せを求めて生きているのです。しかし幸せになるには、幸せであることの十分条件をはっきりさせなければなりません。
先の引用文にもあるように、「幸せを求めて公害を招く」「善いことだけを願って悪いことを排除しようとするその心が、善いことを願う心で悪いことを生み出してしまうのです。」「人間自身が人間を否定するものを自分自身の中から生み出してしまう。」と。
誰もが幸せを求めて生きています。では、幸せとはどういうことなのでしょう。釈尊は王家の世継ぎ(皇太子)でありながら出家されたということは、皇太子という位にあっても幸せではなかったということを物語っているのでしょう。
すべて、自分の思い通りにしたいという限り、悩まなければならなくなるのです。自分の思い通りになる = 私有化意識に立てば、それが破れるときに人は悩まなければならないのです。自分の考えに自分が縛られているからこそ、自分の人生が落ち着きのない空虚なものになってしまうのでしょう。
成人式が1月に行われます。ある父親が成人式を迎えた我が子に「お前も成人式を迎える歳になったか、おめでとう。もうこれからは、お前の好きなことをしてもいい。ただ、自分のしたいことには責任を持たなければいけない。」と言い聞かせ、その時は「俺もまぁ気の利いたことを言った」と思っていたそうです。ところがある時、「ああいう言い方は間違っていた、あんなふうに言うべきではなかった、ということに気がつきました。」と。そして「あんな言い方ではなく、「お前も20歳になったか。20歳を迎えるということになれば、これからは、自分一個の人間が生きるには、どれだけ人に迷惑をかけ、どれだけ世話になっているかわからない、みんなのおかげだということが少しはわかる人間になってもらいたい。」と言うべきだった。」と、しみじみ反省しておられたということを聞いております。
2024年12月26日
お庫裡から 2024年12月

今年も無事に、12月へたどりつきました。
この頃になると、手帳を新しくします。そして来年の予定(毎月決まった曜日にやっているもの)を書き込むと、まだ年も明けていないのに、来年の12月まで予定が詰まってしまいます。
書き込みながら、果たして私は来年の12月まで、この予定をこなせるのだろうかと、若い時には気にもかけなかったような心配が頭をよぎります。
今年も沢山の方の訃報を聞きました。長寿でめでたいと送られる方ばかりでなく、涙・涙のお別れも沢山ありました。
私達の生は、いつも死と隣り合わせにあります。そんな中、私は78歳を迎えました。78歳の私は、私の子どもの頃に見知っている老人の姿とは全く変わっております。まるで老いを忘れさせるマジックにかかっているようです。でも年令は、十分に老人で、死はますます近くに来ています。
私に生まれさせていただき、守綱寺という生活の場をいただき、沢山の方々のお支えをいただき、今があるのは、私にしか歩めない私の人生を歩んでくれよとの、弥陀の願いの成就の姿。
ありがたく頂戴し、ありがとう、ありがとうと、御礼を申しながら、限りある時を歩ませて頂こうと思っています。
(「目は自分を見ることができない。尚子さん、あなたはりっぱな老人の姿をしてますよ。赤いものを着たって、お化粧しててもね。」いやらしいアミダさんの声)
2024年12月26日
今月の掲示板 2024年12月

空っぽ 空っぽ
それを一杯つまっているように見せている
しんどいぞ(松井恵光)
俺は絶対落ち込まないのよ
落ち込む人っていうのは
自分のことを
過大評価しすぎやねん(明石家さんま)
苦し“み”
悩“み”
痛“み”
悲し“み”は
人間の“味”
やらねばならぬと思うなら
やめなさい
やらずにおれないと思うなら
やりなさい(安田理深)
「幸福をください」と
請求書を阿弥陀仏に出すのではなく
「今の私を引き受けました」と
領収書を阿弥陀仏にお届けするのです(米沢英雄)
仏教の教えは
奇跡を起こすメソッド(方法)ではなく
魔術でもない
教義の中では
自然法則の立ち位置にある
仏教は不可能を可能にする
技術を示さない(コード・ブッダ(円城 塔)より)
迷い 悩み 苦しむ
全ては 道を求めてるが故に
「正義」を「自由」を名目に
愚かなことだ
戦争とやら
2024年12月26日
本堂に座って 2024年12月

本山・東本願寺から発行されている『同朋新聞』2024年11月号に、子どもの養育環境の改善に取り組まれている武田信子さんのインタビューが掲載されました。武田さんは、ご自身の経験から「子どもが育ちの中でしんどい思いをするのは、親だけが悪いのではなく、その背景に社会の問題がある、その社会のあり方そのものを問うていかなければならない。」との思いをお持ちです。武田さんが話された親子の関係について(今月と来月の2回に分けて)紹介します。
――武田さんは「エデュケーショナル・マルトリートメント」という問題に取り組まれていますが、これはどういうことでしょうか。
エデュケーショナル・マルトリートメントとは、親を含む大人が子どもに対して教育やしつけのつもりで行う、子どもの心身や脳を傷つける行為のことで、教育虐待なども含まれます。教育虐待とは、教育に対して子どもに過度に期待し、子どもの人権を無視して勉強や習い事などを無理強いすることです。家庭内で起こるものですが、教育虐待を親だけのせいにして、親を責めたところで、根本的な解決にはつながりません。「虐待」と呼ばれるまでに子どもに大きな期待をしてしまう背景にあるものは何か。教育虐待が私たちの社会構造の中で起こっているのであれば、その社会に生きている私たち一人ひとりが責任を持って、社会を変えていかなければいけないと考えています。
最近は子どもに悪影響を及ぼす親のことを「毒親」とも言われますが、そういった悪影響を及ぼす行為や価値観は、この社会の中で生まれているのです。親はそれぞれの価値観の中で精いっぱい子育てをしているつもりなのですが、考え方もやり方も間違えていて、子どもに加害してしまう。なぜ親も子もこんなに苦しまなければいけない社会なのか。だから私は、エデュケーショナル・マルトリートメントといった言葉を使いながら、「こんなひどい親がいますよ」ではなくて、こんな親が隣の家にいるのに何もできていない自分はいったいどうしたらよいだろうか」を問える社会にしませんか、ということをお伝えしています。
――「子どもたちが、昔に比べておとなしくなった」といった話を聞きますが、それは教育の効果によるものなのでしょうか。それとも、また別の原因があるのでしょうか。
赤ちゃんとその親が何人か集まっているひろばなどでは、赤ちゃんが興味を持ってハイハイで、他の子に近づこうとすると、ほとんどの親がぶつかることを避けて、後ろから止めます。あるいは、おもちゃが1個しかない場合、別のおもちゃを与えて、取り合いにならないようにします。本当は、そこで取り合いをすることによって、子どもたちは人との距離の取り方などを覚えていくのです。おもちゃをそれぞれに与え、人とトラブルにならないようにすると、けんかは起きませんが、人間関係を学ぶことができません。実は、物を取り合うことも大切な経験で、必要なことです。子どもたちは、赤ちゃんの時点から、やりたいこと、興味を持ったことを止められています。動物には、みんな主体性がありますよね。だから本来、主体性のない赤ちゃんなんていないはずですし、もし主体性のない子どもたいるとしたら、それは、生まれてからこれまでに何か主体性を持つことを止められた経験があるということです。
今は赤ちゃんの話をしていますが、赤ちゃんが大人になるわけですから、土台の部分は変わりません。学校でも、生徒が聞いたことにうまく先生が答えてくれなければ、だんだん子どもも先生に聞きに行かなくなります。他にも、授業中などは間違えて当然なのに、間違えると、みんなに笑われる。それを繰り返していたら、みんな発言しなくなりますよね。子どもたちに反発を許さず、大人が決めたとおりに従うように育てることを、教育の成果と言うかどうか。子どもに覇気がないなどと言われますが、結局、それは欲求や怒りなどの感情をすべて抑えられて、子どもが諦めているだけではないでしょうか。
(『同朋新聞』2024年11月号 東本願寺出版発行
人間といういのちの相(すがた)「社会の中で「子ども」は育つ」より引用しました)
2024年12月26日
今日も快晴!? 2024年12月

11月16日(土)&17日(日)と、無事に報恩講が勤まりました。15日(金)の準備から、大勢のお檀家の皆さまにお手伝いに来て頂き、本当にありがとうございました。また、守綱寺の檀家でなくても、門徒会の方や、お寺で毎月行っているお稽古事の生徒さんや育児サークルのメンバーなど、様々なご縁の方に準備やお参りに足を運んで頂くことが出来て、本当に嬉しく思います。
守綱寺では、報恩講のお飾りのお団子=お華束(けそく)さんを手作りしています。金曜日は、米粉を蒸して臼と杵でつき、型を抜き、串に刺して色を塗り、台に飾り付けて本堂に飾るところまで行います。コロナ以降、簡略化が進み、手作りすることや食事を控えるケースが多い中、以前と変わらず一から全て手作り出来ているのは凄いことだなぁと思えます。「報恩講だから、やらにゃいかん」というお檀家の皆さまの心意気を感じて、本当に心強く思います。阿弥陀さまの前では皆平等という心地良い空気感の中で、皆でわいわいお喋りしながらお餅をついてお団子を作り、野菜の下ごしらえをする金曜は、まるで文化祭の準備のようなワクワクとした楽しい一日です。今年は高校2年生の娘がラーケーションを取り、学校を休んで参加してくれました。若い力が頼もしく感じられます。
面倒なことを避けたり、お金で解決しようとしたり、コスパ(コストパフォーマンス)やタイパ(タイムパフォーマンス)という言葉が大流行ですが、そうした流れに逆行するかのような「全部自分たちの手で作り上げる報恩講」は、それだからこそ「自分たちの報恩講」になるのだと思えます。便利なことや面倒が省けることは良い面も確かにありますが、わざわざ時間を掛けてすること、実際に自分の手を動かすこと、様々な人たちと協力しながら作り上げること・・・そうした面倒で手間暇掛かる事の中に、実は大切なものが含まれている気がします。
自宅や学校、職場でもない第三の居場所=サードプレイスという言葉も言われていますが、お寺はいくつになっても足を運ぶことが出来て、仕事も役目もある最高のサードプレイスだと思います。お寺の行事では、60代、70代はまだまだ若手。80代でようやくベテラン、90代でもまだまだ現役で大活躍。「自分はまだまだ若い。お寺に行くのは、もう少し年を取ってから」と思われる方も、是非足を運んでみて下さい。本当に年を取ってからでは、新しい場所に顔を出すのは億劫なので、早いうちにお寺に顔を出すことに慣れて貰えたら良いなと思います。そして、高齢の方がお寺で自分の居場所や役割を見つけて、生き生きと過ごされている姿を見ると、こちらも元気を貰えます。人生の先輩が語られる話は、隣で聞いているだけでとても勉強になります。せっかくお寺とご縁を持って下さったのですから、来年の報恩講は、お参りはもちろんお手伝いの方も是非足を運んでみて下さい