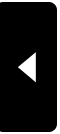2023年06月10日
本堂に座って 2023年4月

先月に引き続き、今回も『不親切教師のススメ』から文章を紹介します。
教師の立場として、本当の意味での「親切」「不親切」とは何なのか、どこにあるのか?をわかりやすくまとめてくださっています。
【おわりに】
本書を一通り読んでもらえるとわかる通り、実は不親切教師の目指すところとは、本当の意味での親切教育である。
子どもが主体的に育つことで、親や教師の手を離れ、あらゆる問題に自ら立ち向かい解決しようとするようになる。
子どもの人生が子どものものとなり、同時に親や教師もそれぞれの人生を自分のものとすることができる。
つまり、お互いが自由になれるということである。相手のことを心から強く思い行うことが親切であるならば、教育における真の親切とは、あれこれ世話を焼くことではなく、子どもを自立へと促す行為である。
これまでの教育はどうしても「横並び」「揃える」「みんな一緒に」という方向性が強かった。
経済成長が上向きの時代においては、周りに言われた通りに動くことで人生が安泰だったからである。
それが時代の要請する最適解だったといえる。しかし日本という国の成長が誰の目からも明らかに右肩下がりになり傾いてきている今、それでは上手くいかないことに人々は気付き始めた。
そこに上乗せする形で教育界には突如「個別最適な学び」というスローガンが出てきて、一人歩きし始めた。
このままでは上手くいくはずがない。
今までと真逆の方向性のものをそのままとり入れたら、矛盾し混乱が生じる。
一種類の作物を育てようとしていた土壌に、それぞれ全く異なる種の作物を植えて一律に育てようとすれば、上手くいかないのは目に見えている。
土壌から、作り直す時である。育つものも「違っていい」ではなく、「違う方がいい」というのを常識にしていく時代である。
「個別最適な学び」を本当に追求していこうというのであれば、子どもたちはそれぞれに個性的であることを改めて認識し直すところからである。
子どもたちは、それぞれ異なる「種」を持つ。
故人だが、私の初任者指導を担当してくださった遠藤満先生という方は、「子どもは作物を育てるように」とよく仰っていた。
まず、コンテストに出す菊のような揃ったものを作ろうとしてはいけないということ。
次に、どんな作物もどんな形のものも大切にすること、それぞれに異なる合った環境があるということ。
植えてからどうこうよりも、それ以前の土づくりが全てだということ。芽が出て弱いうちは水やりや虫の駆除も必要だということ。
それがどれだけ大きくなるかは、小さい段階だと全くわからないということ。ある程度まで大きくなったら後は勝手に育つということ。
不親切教師の目指す主体性を伸ばす教育は、子どもの「種」に内在する力を引き出す手伝いをすることである。
それが最終的に、全ての子どもにとって公正な質の高い教育を提供することへとつながる。そして教育において子どもたちは「教えてもらう」「管理される」受動的な存在から、「自分で考えて学ぶ」「自分で責任をもって行動する」という主体的で自立した存在となっていく。
本書における不親切教師のススメとは、即ち自立型人間を育てるための心構えとその方策を説いたものである。
(『不親切教師のススメ』松尾英明 著 さくら社発行より引用しました)
子どもが困っている様子を目にすると、「何とかしてあげたい」と思い、動いてあげることがあります。
その際に、「何を」「どこまで」してあげるか(してあげないか)…が大切だと、この本の中では具体的に実例が挙げられています。
子どもの様子をきちんと見て、必要最小限な分だけ手を差し伸べることが、結果として子どもの自立を促すことになると教えてくださっています。
2023年06月10日
今日も快晴!? 2023年4月

約3年前に代替わりをして、それまで父と母でやっていた仕事を徐々に譲り受けることになりました。
まだまだ分からないことばかりで、母と同じようには出来ませんが、父母が元気なうちに交替してゆけるのは本当にありがたいことだと思います。
中でも、「お寺参り」の仕事は、本当に学びの多い場になっています。
「お寺参り」とは、お葬儀を済まされたご家族の方が、お寺に足を運び、本堂(冬期はお内仏の部屋)でお勤めのあと、今後のお仏事の日程などを相談する場です。
ご葬儀を終えられた直後のご家族の方と色々とお話させて頂くと、亡くなられたときのご様子、ご家族の思い出等々、本当にどれ一つとして同じお葬儀は無く、それぞれが大切なご家族の方との関係の中で、唯一無二のかたちでいのちを終えられて行くのだということをつくづくと感じます。
ご自宅で長く介護をされてきた方が、寺参りの席でぽつりと言われた「…寂しくなっちゃったな。」という言葉が印象に残っています。
「介護」と聞くと、終わりが見えず大変なイメージや、介護疲れによる虐待や暴行のニュースを目にすることも多いので、「(亡くなって)ホッとした。肩の荷が下りた。」といった言葉が聞かれるのかなと思っていたのです。
けれども、そんな私の浅はかな予想に反して、家族の不在を悲しむその言葉を聞いた時に、なんて尊いのだろうと感じました。
たとえ寝たきりでも、介護を必要とする状態であっても、どのような状態であっても、亡くなって良い命など一つも無く、その人にしか出来ない役割があるのだと教えて頂きました。
また、ご自宅でお葬式をされたご家族の方にお話を伺っていた時のことです。
「おばぁちゃん、綺麗にお化粧してもらって、10歳くらい若く見えて良かった」、「おばぁちゃんの好きだった着物を着せてあげられて良かった」、「毎日のように身につけていた帯を、私が繕って付けてあげられて良かった」、「自宅葬だったので、近所の方が普段着のまま気軽に来て手を合わせて貰えたので良かった」と、「良かった」という言葉が何度聞かれたか分かりません。
悲しみの場であるはずのお葬式が、こんなにも「良かった」という気持ちで満ちあふれ、満足して終えることが出来るなんて、これこそが本来の葬儀の姿なのでは無いかと強く感じました。
そして、その場を任される僧侶という仕事が、お寺の役割がどれだけ重いものであるか、改めて感じずにはいられません。
私が小学生だった頃、ある男の子に「おまえん家、寺だろう。お葬式で金儲けしているんだろう。お賽銭で生活してるんだろう。」と言われたことがありました。
本当に悔しくて情けない気持ちになりました。
でも今は「葬儀を任される」ということが、どれだけ尊いことなのか。
年を重ねて、少しずつ分かるようになりました。
「命を終える」という行為は、誰もが人生でたった一度だけ経験するものです。
その時を、本当に満足する形で終えられるかどうか。
「満足」というのは、お金を掛けたり派手なことをするということではなく、 亡くなられた方が寿命を精一杯生ききられたことを尊び大切に受け止めることで、そうでなければ、後に残された方達が自分自身を大切にすることも出来ないのではないかと思えるのです。
大切なご家族が亡くなられたとき、「どこでも良い」ではなく、「守綱寺に頼む」と言っていただけるのは、本当にありがたいことだと思えます。
そういって守綱寺を選んで下さるお檀家の皆さんに、「守綱寺で良かった」と言ってもらえるように、精一杯勤めさせて頂きたいと思います。