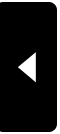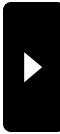2024年07月08日
清風 2024年7月

実るほど
頭を垂れる稲穂かな
実ると頭を垂れる稲穂のように、人間も青年・壮年・老年と歩みを
進める中で、その人柄が謙虚になる(成熟する)ことに例えられる。
先月号の巻頭では「人間(私)は 与えられているから 悩む」という言葉を挙げ、水木しげるさん(漫画家:ゲゲゲの鬼太郎の作者)のエピソードと短歌「論の沸く 後期高齢 めでたけれ 52歳の 亡夫は老いえず」を紹介して、「人生に花開く」とはどういうことなのかを考える一助にしたことでした。
<脈はく>
一分間に六十五 キチンキチンと 休まず止まらず 打ち続けて六十余年
あと何年か何日か 眠っておっても愚痴っておっても 休まず止まらず
宇野正一(岡崎出身 詩人)『樹に聞く花に聞く』より
私たちはこの脈はくを感じておるのでしょうか。「眠っておっても愚痴っておっても」我々は寝ておっても明日目が覚めるのは、脈はくが眠らずに打っておってくれるからでございましょう。「一分間に六十五 キチンキチンと休まず止まらず 打ち続けて六十余年 あとは何年か何日か」それはわかりません。いずれは止まります。生まれたということがあれば、いずれは死なねばならないからとまります。
その間ただの一分間も休まない脈はくが、三分間停滞したら私たちの脳のはたらきは停止します。たとえその後生きておりましても、植物人間になってしまうのです。だから今日までしゃべることも出来れば、足を運んでここまで来れることのできたのは、ただの三分間脳へ新しい酸素を送られることが、休むことがなかったという事実を、我々に明らかにしているんです。その事を私たちは気付いているのでしょうか。眠っていても、愚痴っておっても休まず止まらず、そういう脈はくのはたらきによって、私たちは生かされて生きているのでしょう。
(『如来に遇う』松扉哲雄 桑名別院発行 平成元年刊より)
今月も、もう少しその視点から考えてみたいと思い、論を進めていきます。
さて、同じく先月号の「今月の掲示板」で、次の言葉を紹介しています。
この世界には 最初から 生まれて来て 良かった存在も
生まれて来なければ良かった存在も ないんだ
そうです。気がついた時には生まれており、ここまで育てていただいてきたわけです。この両親の元に生まれようとして生まれてきたわけではありません。これは親からしてもそうですが、今では「親ガチャ・子ガチャ」という言葉にもなっているように、親は子を選べず、子も親を選べない、ということです。
しかし医学の進歩というかAI(人工知能)等の成果によって、人工授精による妊娠も可能となったのですが、やはり生まれて初めて、そして育ってみないと、結局のところは「親ガチャ・子ガチャ」で、どうなるかはわからないのです。
現代の私たちが一番見過ごしている問題提起だと思い、今あらためて次の言葉を紹介する次第です。
私は十数年ぶりでヨーロッパから戻ってきたのですけれども、日がたつにつれて、これは多少異った表現を用いて、皆さん表現しておられるけれども、何か大きな空虚が日本人の思想の根底にあるのじゃないだろうか、ということが、だんだん明らかになってきたわけです。 (対談冒頭の言葉)
結論的には、現代の日本の文化がかなり特別な症状をしているということで、私は、一言でいえば、生きるということの根本感覚が喪失し、生きるための手段で困憊しているのだと思います。ここで、一度すぐ目に見える有効なものをはなれて生活するということの根本にたちかえり、その点からすべてを見直すということはどうしても必要です。(対談文末の言葉)
「技術時代と思想」(『朝日ジャーナル』1966年12月11日号)
森 有正 1953年デカルト研究のため渡仏、以来パリ定住。
1966年9月に帰国し、11月ふたたびパリに戻った。
上記は武田泰淳(作家)との対談から。
註)『朝日ジャーナル』は1959年3月15日から発行、1992年5月に休刊。
1993年に主な連載を掲載し、『朝日ジャーナルの時代』として刊行された。
この対談も、1993年刊の『朝日ジャーナルの時代』に依る。
「生きるということの根本感覚が喪失し、生きるための手段で困憊している」という指摘について、引き続き考察したいと思っています。
2024年07月08日
お庫裡から 2024年7月

「尚子さん、こんなチラシが入ったんだけど。これってお寺でよく聞く『歎異抄』のことだと思って。でも、チラシのどこにもお寺の名前が書いてないので、行っていいのかどうか、教えてもらおうと思って」と一枚のチラシを見せてくれました。
それは、近くの交流館で開く「歎異抄をひらく」というチュー○ップ企画のアニメの上映会の案内でした。
4月にも、もう一人の友人から「家の近くの交流館で、しんらんさんの映画会があったんですよ。丁度、しんらんさんのことが知りたいと思ったので行ってみたんです。
終わってから、次から勉強会がある、その申し込みをと言われて、名前を書いてきたのだけれど、何だか、どこか、ここのお寺で聞いているのと違うような気がして、たずねてみました。」
この方も、チラシと同じチュー○ップ企画の上映会でした。
また、今年のお正月、お墓参りに見えたご夫婦が、玄関へ顔を見せてくださり、ご主人の方が「最近、私ね、しんらんさんの勉強してるんですよ」とやや自慢げ、すると奥さんが「もう人がいいからだまされてるんですよ」「そうかなー」「そうよ、会費が最初3,000円と言ってたのに、今50,000円要求されてるじゃない」「やっぱり、だまされてるのかなー」
そのご主人の方に、「勉強しておられるのは親○会という会ですか」とたずねると「そうです、そうです」というご返事。
親○会は新興宗教で、チュー○ップ企画という名で活動しています。
しんらんさんに関心をもっていただくことは大変ありがたいことですが、ご不明な時は、お寺にお問い合わせください。
2024年07月08日
今月の掲示板 2024年7月

この花は
この草にしか咲かない
そうだ
私にしかできないことがあるんだ
比較した時から
苦しみが始まる
なんでもない なんでもない
なんでもない なんでもないことが
こんなに うれしい
微力だけれど
無力ではない
人生で何かにぶつかったら
それは壁ではなく
扉なのです
わたしは例外
わたしは特別
ついつい 思いがち
現実は変えられないが
視点を変えることはできる
消しゴムの仕事は
「間違うな」ではなく
「間違っても大丈夫!」と
鉛筆を安心させること
怨みに怨みを以て報いるならば
決して怨みはやまず
ただ怨みは捨ててこそやむ
(法句経 釈尊のことば)
何でもないようなことが
しあわせだったと思う
(THE虎舞竜「ロード」)
2024年07月08日
本堂に座って 2024年7月

このところ、(仏教書ではなく)一般の書籍で親鸞聖人のお言葉が取り上げられることが増えている感があります
(たまたまそういう本を手に取っているだけかもしれませんが…)。
そんな中、作家の高橋源一郎さんが『歎異抄』を“いまのことばに少しだけ変えて”届けてくださっています。
その中からよく聞かれる「悪人正機」について書かれた第3章を紹介します。
<その三 悪人だからこそゴクラクに行けるんだ>
あるとき、「あの方」はぼくにこういった。
「善人でさえ、死んでからゴクラクジョウドに行くことができるのだから、悪人なら当然行けるはずだ。おれはそう思うんだ。わかるかい、ユイエン。ふつう、そうは思わないだろう。『あんなひどいことをした悪人でさえ、救われてジョウドに行けるのなら、善人はもう無条件でゴクラクジョウド行き確定だよな』って思う。それがふつうの考え方だ。
確かに、ぼんやり聞いていると『ふつうの考え』の、その論理は正しそうに思える。ユイエン、でもそうじゃないんだ。それは、おれたちが信じている『本願他力(ホンガンタリキ)』、つまり『すべてをアミダにおまかせする』という考えから遠く離れた考えなんだ。
善人というものは、もっと正確にいうなら、自分を善人だと思いこんでいる人間は、なにかにすがらなきゃ生きていけないというような、ぎりぎりに追い詰められた気持ちを持ってないんだ。なにか善いことをしてその見返りでゴクラクオウジョウできるんじゃないかって思ってるんだ。こころの底ではね。それじゃダメなんだ。そういう計算ずくの人間たちを救うことは、アミダにだってできないのさ。
でも、そんな善人だって、ちっぽけな自分にできることなんか実はなにもないと気づいたなら、なんの力もないのだからアミダにおすがりするしかないと思えるようになったのなら、そのときには、ほんとうのジョウドというところに行くことができるんだと思う。
いいかい、ユイエン。おれたち人間はどうあがいても、欲望からも苦しみからも逃れることはできない。絶対に、だ。どんなにすごい修行をしても、生きることの苦しみ、死なねばならないことへの恐れを忘れ去ることはできない。おれたちは、人間である限り死ぬまで苦しみつづけるしかないんだよ。アミダはそんなおれたちを憐れんでくださった。救ってくださろうと、誓いをたてられたんだ。
ユイエン、悪人ってなんだ? おまえにはわかるか? 生きてゆくためには、どうしても悪を選んでしまう人間のことだ。どうして人は、どんな悪とも無縁で生きてゆけるだろう。そもそもほかの生きものの命を奪わなければ、生きてはいけないというのに。
だから、ユイエン。おれたち人間はみんな生まれついての悪人なんだ。そんな、悪人として生きるしかないおれたちを、アミダは救ってくださろうというんだよ。
だとするなら、自分には、救われるための資格なんかなにもないと最初からすべてをあきらめ、アミダにおすがりするしかないと考えている悪人こそ、いちばんジョウドに近い人間ではないだろうか。
自分の中にある悪に気づかない善人でさえ、ゴクラクジョウドにオウジョウできるとしたら、自分の悪を見つめて生きるしかない悪人なら、当然オウジョウできる、というのは、そういう意味なんだよ。」
(『一億三千万人のための『歎異抄』』高橋源一郎 著 朝日新書 より引用しました)
高橋さんは「これからぼくは、みなさんと「シンランのことば」について考えてゆくつもりだ。
そのためには、「シンランのことば」を直接、みなさんに届けたいと思う。
けれども、700年前の読者と、いまの読者とでは条件がちがう。
ほんとうはわかりあえるはずなのに、時間が読者と作者を引き裂いてしまった。
だからぼくがちょっとだけお手伝いをします。
「シンラン」がいま生きていたとしたら、きっとこういうだろうな、そんなことばに少しだけ変えて、みなさんに届けるつもりです。」と冒頭に書かれています。
本来は原文を読み深めたいところですが、『歎異抄』に触れていただくきっかけの一冊に、とてもわかりやすくて良い本です。
2024年07月08日
今日も快晴!? 2024年7月

今年に入り、4月と6月と立て続けにお寺を会場としたお葬式がありました。
最近では葬儀会館を利用される方が増えたので、お寺を会場としてのお葬儀は20年ぶりのことでした。
4月のお葬儀では、夜中の2時に電話が鳴り、「父が亡くなりました。
お寺でお葬式をあげてもらえないだろうか?」との第一報から、ご遺体がお寺に運ばれ、湯灌の儀からお通夜、お葬儀といった故人を送る一連の流れに、ご家族の方と一緒に立ち会わせて頂きました。
早朝の日が差し始める凜とした空気の中、ストレッチャーに乗ったご遺体が参道を上がって来られる様子を、本堂の階段に座って見つめていましたが、怖いとか気味が悪いとか、そんな気持ちは全くなく、ただただ神々しく、なんとも清らかで厳かな心持ちでした。
ご家族の方から、「悪いね。迷惑掛けるね。おじいちゃんはお寺が大好きで、『わしが死んだら、お寺で葬式をあげてくれ』と口癖のように言ってたから…」と言葉を掛けて頂きました。迷惑なんてとんでもない。お寺にとって、これ以上の嬉しい言葉はありません。
私が小学生だった頃、近所の男の子(もう誰かは忘れてしまいましたが)から、「おまえん家(ち)、寺だろう。お葬式で金儲けしているんだろう」と言われたことが、ずっと心に引っかかっていました。
子ども心に、とても傷ついたのだと思います。
けれど、それから40年以上の月日が流れ、今、「わしが死んだら守綱寺に頼む」という一言が、どれほど尊いものであるか。
その方の人生の最後を託されることの重み。
どんな時間でも「お寺に任せた」と運び込んで頂ける信頼関係があるというのは、誇らしくもあります。
卒業式や入学式、結婚式は何度も挙げることが出来ますが、お葬式はその人の人生でたった一度の大切な儀式です。
お葬式を任されるというのは、本当に色々な意味で重みがあります。
また、続いて6月に行われたご葬儀では、独立して実家から離れて暮らすお子さん達が、ご弔問に来られた大勢の方達から、「お父さんには世話になった」、「○○の活動で、本当に世話になった」、「△△でご一緒した」と、声を掛けて頂いていました。
故人が地域で活躍される様子は、お子さん達には知らない一面だったようで、「うちのおやじは、本当に地域の皆さんのために色々な活動していたんですね」、「知らなかった」と、悲しい中にも笑顔でそうした言葉を聞いていらっしゃいました。
これは、家族葬では決して出会えなかった人たちで、ご家族の方達は、亡くなられた方と葬儀を通して再び出遇い直すことが出来るのだと思いました。「周囲に迷惑を掛けたくない」と、家族葬を選ばれる方が増えましたが、亡くなられた方を本当の意味で尊重するというのは、その方のこれまでの人生で出遇った人たちを丸ごと引き受けるということで、お葬式を通して、故人と関係のあった方達に会い、言葉を交わしたり、家族が知らなかった一面を教えて頂いたりすることは、意味のあることなのだと思えました。お葬式というのは、やはり大切な儀式の場なのだと、久しぶりにお寺を会場としたお葬式を通して改めて気づかせて頂くことが出来ました。
今、小学生の自分に会うことが出来るなら、「あのね。お葬式って大切なお仕事なんだよ。その人の人生の最後の儀式を託されるって、ものすごく尊いことなんだよ。自信を持って、全力でお寺の仕事をやれば良い。胸を張ってお葬式をやらせて貰えばいいんだよ。」と話してあげたいと思います。
2024年07月08日
清風 2024年6月

人間(私)は
与えられているから
悩む
寺報「清風」2021年12月号「今月の掲示板」より
この言葉は私の中で生まれてきたのですが、かなり長い年月をかけて成長してきたように思います。
それが、『ゲゲゲの鬼太郎』で有名な漫画家・水木しげるさんの、次の言葉にふれた時でした。
それは、水木さんが何かの賞をいただかれ、そのお祝いをする席でインタビューを受けられた際に「水木さんにとっての幸せをお聞かせください」と問いかけられた時、ほとんど間髪を入れることなく返された「呼吸のできることです」という言葉です。
この言葉には、インタビュアーも返す言葉がなく、そのまましばらく沈黙が続いたそうです。
この言葉が返された背景には、次のようなことがあると思われます。
水木さんは先の戦争で徴用され、戦場で左腕に銃弾が当たり、付け根から切り落とされて敗戦後帰国されました。
その後漫画家の道を歩かれることになりますが、その時代の漫画は一コマごとに描いていかねばなりません。
(今なら、それこそAI(人工知能)を使い、かなり手間が省けるようになったそうですが。)私も両腕がありますので知らなかったのですが、片腕が無いと、身体は腕がある側に傾いてしまうのだそうです。
水木さんは左腕を無くされているので、右腕の関節部分で身体を支えながら、同じ右手で絵筆を使わねばならず、体力の消耗もあって、書き慣れるまでには大変なご苦労があったようです。
こうした経緯もあり、先程のインタビュアーも水木さんが「左腕があれば、どんなに幸せだったか」と思われたであろうと推察して質問されたのでしょう。
ところがまったく予想しなかった言葉が返ってきたことで、しばらく次の問いかけができなくなってしまったのでしょう。
左腕が無くて辛いと思うことも、それは「呼吸ができてのことだ」と。
水木さんも、その事実に気付かれるまでには相当な時間を要したに違いありません。
この水木さんの言葉が出てきた背景を考える時、我々現代人は、「当たり前」という言葉によって、見失ってしまった世界の大きさに触れることができなくなってしまった世代なのだと言うほかないのだと思わされることです。
便利さと快適さを求めて、科学の力を借りて進化・進歩してきた結果、結局は「人間とは、その知恵ゆえに、まことに深い闇を生きている」(高 史明)ということに気づけずに生きているのです。
つまり「当たり前」という言葉で、見失ってしまった世界があるのだということです。
もう一つの例は、「後期高齢者」という用語が高齢者の福祉政策をめぐって制度化された時に話題となったのですが、そんな折、新聞の短歌欄に次の歌が寄せられたのを見たことです。
論の湧く 後期高齢 目出たけれ 52歳の亡夫(つま)は 老い得ず
「後期高齢者」とは何事か、もう「死ね」ということか、後期高齢者…「うん、わしもこれで法律でも認められた歳になったというわけで、大きな顔をして生きていける」、など読者からの「声」(投稿欄)を賑わしたことがありました。
(短歌では、亡くなった連れ合いが男性の場合でも、亡夫と書いて「つま」と呼びます。)
言うまでもないことですがこの短歌は、「私の夫は52歳で亡くなりましたので、後期高齢者である75歳を迎えることができませんでした。
考えてみれば75歳を迎えられた方々は、大変めでたいことじゃないでしょうか」と言われています。
しかし75歳を迎えた人にとっては、それは「当たり前」のことであり、わざわざ他人からとやかくいわれるのは…ということなのでしょう。
我々現代人は、居ながらにして世界中のすべてを見ることができるようになりましたが、自分自身を見つめる眼を失ってしまったのでしょう。
人生に花開くとは この自分が 押しいただかれたことです(野田風雪師)
そしてこんな俳句もあります。
稔るほど 頭を垂れる 稲穂かな
「人生に花開く」とは、この俳句に詠まれているような世界を指すのでしょう。
Posted by 守綱寺 at
13:42
│Comments(0)
2024年07月08日
お庫裡から 2024年6月

6月には父の日、父のことも書いてみようと思います。
父は9人兄弟(7男2女)の末っ子で、名前を有終と言います。
たくさんの兄弟なのに戦後を生きたのは2人の姉と8番目のすぐ上の兄の4人だけでした。
さて、父を語ろうとすれば、子どもの頃から面白いエピソードがいっぱいある人で、この紙面だけでは語り尽くせないほどです。
当時としては170cmと背も高く、がっしりした体格で、声も大きく姿勢よく、一見堅物でした。
おべんちゃらや追従は大嫌い、私たちの育つ頃はどこでもそうだったかもしれませんが、父と話す時は姿勢を正し、敬語を使い、今のように父娘が友人みたいに喋るということはありませんでした。
しかし本当は軟派で、末っ子の甘えた、多い兄弟の育ちか気配りの人、ユーモアが大好き、お話を作って家族を喜ばすのが好きでした。
「わしは小説家になりたかった」と漏らしたことを憶えています。
桑名中学の時、出席を取る先生が父を「三浦丙しゅう」と呼んだところ、すぐ立ち「成績は丙を取ったかもしれんが、親に付けてもらった立派な名前があるのだから、有終と呼んでくれ」と申し立てたそうです。
丙を取ったという父に読めない字を聞くと、どんな字もすぐスラスラと答えてくれたので、丙なのにすごいと変な感心をしていました。
戦後の経済成長の中で、新しもの好きの父は、ステレオ・テレビ・洗濯機・掃除機・冷蔵庫と次々と買い、母を一時困らせましたが、家電の便利さを知った母が喜ぶ姿に「よかったやろがー」と満足気な父でした。
こうして父のことを思い出せる私は幸せです。
夫は父を知りません。
2歳で生き別れ4歳で死別しているからです。
結婚をした時、父は夫のことが気に入り、夫もよく父に会話を合わせてくれたので、私は夫のお陰で親孝行が出来たような気がしました。
その父も亡くなって25年になります。
2024年07月08日
今月の掲示板 2024年6月

この世界には
最初から生まれて来て良かった存在も
生まれて来なければ良かった存在も
ないんだ
他人にどう評価されるかじゃなくて
自分が生きているっていう
実感を求める
それでいい
思い通りにならないこと
うまくいかないこと
失敗すること
誰かに負けちゃうこと
なにかをあきらめること
…これからもいっぱいある
でも終わりじゃない
戦争はいったい誰のためにするんだろう
こんなに破壊し尽くして人を殺して
何を得るというのだろう
咲くも無心
散るも無心
花は嘆かず
今を生きる
名が出ない「あれ」「これ」「それ」で用を足す
景色より トイレが気になる 観光地
「こないだ」と五十年前の 話する
骨と皮 まだ頑張るぞ スジがある
2024年07月08日
本堂に座って 2024年6月

先日、チラチラとFacebookを見ていたところ、ある方が相田公弘さんの記事をシェアされていました。
学校での出来事ということもあり何となく読み始めたところ、思わず引き込まれ、最後まで読み進めました。
モンスターペアレントや、過保護すぎる親が溢れている昨今。
そんな中、とある都内私立小学校の授業参観での出来事が、大きな波紋を呼んでいます。
例に違わず、過保護すぎる親がたくさん参加していた授業参観。
教室の中ではある題材の作文の発表が行われていました。
発表中にも関わらず、子供を褒めたり、また教室の清潔さにケチをつけたりと、先生も思わず苦笑いをする親たちの発言。
そうした時に、一人の小学生が手を挙げ次の発表をしたいと立候補をしました。
その発表が、教室の空気と過保護な親たちの意識を大きく変えることになったのです。
この授業参観の中で発表する作文の題材は「家族への想い」でした。
家族に対しての気持ちを作文にし、発表するというもの。
手を挙げた小学生は堂々と作文を読み上げました。
『信じあうこと』
私は、家族が大好きです。家族も私のことが大好きです。
でも、たまにとても悲しい気持ちになることがあります。
私の家族は、いきすぎだと思うほど私のことを心配します。
この前、私は〇子ちゃんとケンカをしました。私は、〇子ちゃんに嫌なことをさせられました。でも私も〇子ちゃんに嫌なことをしたと思い、仲直りをしたいと考えていました。
その時に、お母さんは私にあなたは悪くないと言いました。〇子ちゃんがわるいんだから、あやまらなくていいのよ、と言いました。とてもびっくりしました。なんで私もわるいのに、私はあやまらなくていいのかなって、そのときに思いました。お母さんは、もしかしたら私のことをしんじていないのかもしれないと思いました。お母さんは、『自分の子供』という事を信じているだけで、『自分の子供だから』という理由だけで、私はわるくないといっているんじゃないかなと思いました。
そのとき、とても悲しくなりました。お母さんは、私という人間のことを信じてくれているのかな?と心配になったのです。私はお母さんの子供だけど、私という一人の人間でもあります。その私という人間をちゃんとみてくれて、知ろうとしてくれて、信じてくれているのかなって、思う時があります。
最近、テレビでモンスターペアレントという、子供のためにいっぱい怒る人が増えているという話をみました。それを見てこの作文を書こうと思いました。きっとそういう人が増えているのは、きっと子供自身を信じるのではなく、『自分が育てた子供』という、育てたこと自体を信じているんじゃないかなって思いました。似ているようで、すごく違う事の様に感じるのは私だけではないのではないでしょうか。
私は、家族が大好きです。だからこそ家族には、もっともっと、私のことを信じて欲しいと思います。信じあうことができたら、きっともっと仲良く、もっと笑顔いっぱいで一緒に居れるんじゃないかなって思います。私も、もっとしっかりして、勉強もたくさん頑張ります。だから、これからも私のことをたくさん信じて下さい。私は、かならず家族みんなの自慢の娘になります。
作文の発表中から、空気が静まり返る感覚がありました。
発表後、授業参観にきていた親たちは、誰も言葉を発する事がありませんでした。
でも少し間が出来てから、先生は大きな拍手をしました。
つられる様に親たちも大きな拍手をします。
発表をした女の子のお母さんは、授業参観後に自身の振る舞いに対して、謝罪をしに行ったとの事です。
間違いなく女の子の発表が親たちの意識を変えた瞬間でした。
この話は、最近教師を退職した方が、一番印象に残っている話として、寄稿してくれたお話です。
子供は大人が思っている以上に、敏感に大人の事を見てくれているのかもしれません。
なんでも大人が正しいと思わず、今一度立ち止まり、自分自身の立ち振る舞いを振り返ってほしい、そんなメッセージが籠っているのかもしれませんね。
(相田公弘さんのFacebook投稿より引用しました)
2024年07月08日
今日も快晴!? 2024年6月

5月に、医師と僧侶という二つの現場で活動されている沼口諭先生の講演を聴きました。
「命を支える医療、いのちに寄り添う仏教~人生の最終段階におけるいのちのケアを宗教者と協働して見えたもの~」という講題で、終末期医療の現場でいのちのケアの実践を通して得られた学びをお話し下さいました。
本当に素晴らしいお話でした。記憶に残る内容を書き留めておきたいと思います。
○医療の現場では、宗教的な活動が必要だと思われる場面がある。
医療も仏教も、生老病死という同じ課題に向き合っている。
○「命」=生物学的生命(有限性)=長生きするにはどうしたら良いか=医学に学ぶ
「いのち」=無量のいのち(無量寿)=どう生きるのか=仏教に学ぶ
○医療モデルの変化。
ただ長生きすれば良いというアンチエイジングな狭義の医療モデルの時代から、地域包括ケアシステム・共生社会における医療に変化して、ウィズエイジング、ミーニングエイジング(意味のある高齢期)にパラダイムシフトしつつある。
生物学的生命から、「ものがたられるいのち」へ。
限りある生に意味を与える・・・これは長年宗教者が行ってきたこと。
○養老孟司…死が見えなくなった現代→80%の人が病院で最期を迎える→生老病死の死が
我々の日常生活の中から見えなくなっていった→死と向き合えない日本人
コロナ禍→感染すると、死に目に会えない。死に立ち会えなくて、在宅医療を選択する人が増えた→スピリチュアルペイン・グリーフを抱える現代
○スピリチュアルな苦痛→自分の存在や意味を問うことの苦痛。死ぬのが怖い。
自分の人生に価値があったのか。
あの時ああしておけは良かった。自分は優しくしてもらえる人間でない(罪悪感)。生きていると迷惑を掛けるばかりだ。なぜ私が癌に罹らなければならないのか?等々。
こうした苦悩は、医療で解決出来ない。
○SBNRスピリチュアル(特定の宗教を信仰しているわけではないが、精神的な豊かさを
求める人々)の割合が、日本では高い。
○欧米では、医療の中に宗教者がいるが、今の日本にはそれがいない。
今、臨床宗教者師が求められており、国立大学でも養成講座が出来ている。
1.東北大学文学研究科実践宗教学寄附講座
2.龍谷大学大学院実践真宗学研究科
3.上智大学大学院実践宗教学研究科、等々・・・。
講演の後半では、沼口先生が開設された「メディカルシェアハウス アミターバ」の紹介があり、臨床宗教師を含めた他職種チームによる医療、介護の提供を行い、「命」ではなく、「いのち」のケアを実践されている様子が紹介されました。
海外の方やキリスト教の方からは、「日本は各家庭にお内仏(仏壇=礼拝の場)があるのは羨ましい。
お寺が行っているお葬式、初七日、七日勤め、月参り、法要等々は死と向き合う大切な学びの場である。
それなのに、なぜその良い習慣を無くすのか?」と言われているそうです。守綱寺もそうした昔から行われてきた儀式を丁寧に行いたいと願いながら、難しい現実に直面しています。
沼口先生から、「今のニーズに合った場を作ることを考えていかれたらどうですか」と、とても大きな課題を頂きました。